
自分の親や身内に対して「もしかして認知症?」と心配になることはありませんか。とはいえ、親が認知症を発症しているかどうかが気になっても、なかなか行動に移せないもの。そんなときは、自宅で簡単にできるセルフチェックを試してみてはいかがでしょうか。チェックしてみてもし気になることがあれば、医療機関に相談してみてください。
目次
こんな人におすすめ
- 自分の親が認知症かどうか、気になっている人
- 自宅で簡単にできる認知症のチェック方法を知りたい人
「親が認知症かも?」と思ったら、まずは初期症状をチェック
認知症は、発症前に対策することや、また発症した後でも、できるだけ早期発見して進行を遅らせるための治療などを行うことが大切です。そのため、親や家族に認知症の兆しを感じたら、すみやかに医療機関への受診を促してください。
しかし、本人が嫌がったり、実家が遠方だったりしてなかなか行動に移せないこともあるでしょう。そんなとき、まずは子ども世代が認知症の初期症状を正しく知り、自宅で簡易的にチェックしてみることをおすすめします。そして初期症状に思い当たることがあれば、早めに医療機関に相談しましょう。
例えば、公益財団法人 認知症の人と家族の会が作成した『家族がつくった「認知症」早期発見のめやす』には、認知症の初期症状のポイントがチェックリストとして分かりやすくまとまっています。この詳細はこちらの記事で紹介しています。ぜひ参考にしてください。
👉 認知症を早期発見するメリットとは? 気付くためのチェック項目も紹介
そのほかの認知症テスト&チェックを紹介

自分で簡単に認知症のチェックができる方法はほかにもあります。ここでは、臨床現場でも利用されている方法を紹介します。
山口式キツネ・ハト模倣テスト
山口式キツネ・ハト模倣テストは、医療現場でも利用されている動作によるチェック方法です。同じ動作を模倣できるかどうかで認知症をチェックするため、場所を選ばずチェックできます。
こちらの記事では、詳しいテストの方法を画像付きで紹介しています。試してみたい方はぜひご参照ください。
👉簡単にできる認知症のセルフテスト&チェックリストを紹介 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
認知症自己診断テスト/一般社団法人認知症予防協会
一般社団法人認知症予防協会が公開している「認知症自己診断テスト[PDF]」は、複数の図版や数字を記憶した上で、「よく読んで数字で答えてください。今年は西暦何年ですか?」など、1〜10の質問に答えることで、認知症の心配がどの程度あるかをセルフチェックできます。3種類のコースがあるので、質問への慣れや答えを覚えてしまうことによる結果のブレを考慮せず、複数回のテストを試すことができます。
自分でできる認知症の気づきチェックリスト/東京都福祉局
東京都福祉局が公開している「自分でできる認知症の気づきチェックリスト」では、「バスや電車、自家用車などを使って一人で外出できますか」など、1〜10の質問に答えることで、認知症の可能性について、おおよその目安をチェックできます。このチェックリストは、家族が本人の代わりにチェックすることも可能です。ただし、日常生活の行動のしやすさなどを意識したリストなので、身体機能が低下している場合は点数が高くなることがあり、判断には注意が必要です。
こうしたテストは、帰省したタイミングなどで親に声をかけ、気負わずにゲーム感覚で取り組んでみるとよいでしょう。その日の体調に結果が左右されることがあるので、調子のよいときに試してみるのがおすすめです。
ただし、これらはあくまでセルフチェックなので、「おかしいな?」と思ったら自己判断せず、専門医に相談してください。
親の認知症をチェックするときに気を付けたいこと

セルフチェックはあくまでも簡易的なものなので、結果をそのまま鵜呑みにせず、気になることがあれば医療機関を受診して医師に診断してもらってください。受診を嫌がるときは、「いつまでも元気でいてほしいから健康診断に行こう」、「私が受診するけど、心細いから着いてきて」のような誘い方も有効です。その場合、事前に受診する医療機関に事情を話しておくと、医療機関側の対応もスムーズになるでしょう。
また、チェックがうまくいかなくても責めたりせず、嫌がったら無理強いしないで機会を改めることも大切です。親を心配する気持ちはよく分かりますが、一方で本人の気持ちに寄り添うことも大事な視点。本人も「なんだかおかしい」と思いながらも認めたくない気持ちが働いていることがありますから、まず子ども世代が正しい認知症の知識を持ち、思い込みで動かないようにしましょう。
親世代の認知症に向き合い、正しい認知症の知識を学びながら笑顔で過ごすだんだん・えむさんご家族の様子を取材した記事がこちらにあります。ぜひ参考にしてください。
👉親が認知症になって分かった向き合い方と備え方。『認知症ポジティブおばあちゃん』の家族に聞いた - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
また、親の様子を見て、「これって認知症? それとも加齢に伴う物忘れ?」と悩んだら、下記の記事も参考にしてみてください。
👉認知症と物忘れの違いは? 症状の比較と対処法を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
認知症の発症リスクを正しく把握し、対策に努めよう
同居している親御さんに対してはもちろん、離れて暮らすご両親が認知症になっていないかどうか、心配する子ども世代は多いはず。「もしかして認知症?」と不安を感じたら、まずは簡単なチェックをしてみてもよいでしょう。ただし、あくまでセルフチェックなので、体調や気分に結果が左右されることもあります。気になることがあれば医療機関で受診するようにしましょう。
編集:はてな編集部
編集協力:株式会社エクスライト
今は認知症の症状がなくても、自分や家族に将来の認知症発症の不安を感じることもあるでしょう。フォーネスライフが提供する疾病リスク予測サービス「フォーネスビジュアス」では、20年・5年以内(※5年以内は65歳以上が対象)の認知症をはじめとした各種疾病の将来の発症リスクを予測できます。さらには結果を踏まえて、コンシェルジュ(保健師)がご自身に合った生活習慣改善方法をご提案しますので、自分では難しい食生活や運動習慣の改善をプロと一緒に進められます。認知症になりにくい生活習慣に向け、今からできることを始めましょう。
※フォーネスビジュアス検査は、医療機関の医師を通じて提供します。

 詳しく見る
詳しく見る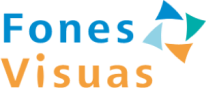
 「フォーネスビジュアス」のサイトを見る
「フォーネスビジュアス」のサイトを見る