
「認知症の予防にはポリフェノールが良いらしい」と耳にしたことはありませんか?本記事では、そもそもポリフェノールとは何か、認知症とどのような関係があるのかについて解説します。また、ポリフェノールが豊富に含まれている飲料や食材も紹介しますので、日々の食生活に取り入れる参考にしてください。
こんな人におすすめ
- 認知症とポリフェノールの関連に興味がある人
- 認知症対策のために、食生活を改善したい人
- 家族の認知症発症リスクを不安に感じている人
ポリフェノールは認知症予防に効果がある?
「ポリフェノール」という言葉を耳にしたことはあっても、具体的にどのようなものなのか、詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。
ポリフェノールは、植物に含まれる苦味や渋味、色素のもとになっている化合物の総称です。フルーツ、野菜、穀物、お茶などに含まれています。強力な抗酸化作用を持っていることが特徴。この抗酸化作用が認知機能の低下を予防する上で重要な役割を果たすと考えられています*1。
聞いたことのあるあの成分も、実はポリフェノールの一種
ポリフェノールは身近な食材に数多く含まれています。例えば、緑茶に含まれるカテキンや、大豆に含まれるイソフラボン、ブルーベリーなどに含まれるアントシアニンも、実はポリフェノールの一種なのです。
これらの成分は、健康に関わるさまざまな効果が確認されています。また、身近な食材から手軽に摂取できるため、健康サポートの頼もしい味方といえるでしょう。
ポリフェノールを豊富に含む食品とは?
ここからは、手軽にポリフェノールを摂取できるおすすめの食品を紹介します。
コーヒー・緑茶

コーヒーに含まれるポリフェノールの一種であるクロロゲン酸には抗酸化作用があり*2、認知機能低下の対策に役立つとされています。また、緑茶に含まれるカテキンには抗酸化作用や抗炎症作用があり、アルツハイマー型認知症の原因物質である異常なタンパク質・アミロイドβの蓄積を抑制するという報告も*3。
ポリフェノールではありませんが、カフェインにも認知症対策への効果が期待されており*4、健康的な習慣として取り入れる価値があります。
赤ワイン

赤ワインには、アントシアニンやレスベラトロールといったポリフェノールが豊富に含まれており、高い抗酸化作用があります。適量の赤ワイン消費(1日250~500ml程度)が認知症の発症リスクを抑えるという報告もあります*5。ただし、アルコールの飲み過ぎは健康を害する可能性があるため、摂取量には注意が必要です。
認知症とアルコールの関連性について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
👉認知症とアルコールの関係は? リスクを高める飲酒量について解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
チョコレート

チョコレートの主原料であるカカオに含まれるカカオポリフェノールにも、抗酸化作用があります。活性酸素を抑制する働きや、血圧低下、コレステロール値の改善など、生活習慣病の対策に役立つことが知られています*6。
また、愛知県蒲郡市・愛知学院大学・菓子メーカー明治による産学官協同で実施された大規模な実証研究*7によると、カカオポリフェノールの摂取によって、脳由来神経栄養因子であるBDNF※の血中濃度が有意に上昇することが分かりました。
BDNFは、記憶の形成を司る「海馬」に多く存在しているとされ、認知症との関連性が報告されています。
※BDNF:神経細胞の発生・成長・維持・再生を促進させる神経栄養因子で、認知機能との関連が指摘されている
ポリフェノールを含む食品の取り過ぎには注意
厚生労働省が5年おきに改訂する「日本人の食事摂取基準」では、1日あたりのポリフェノール摂取量について、明確な基準は示されていません。
ポリフェノールの摂取を意識することは健康への一歩となりますが、ポリフェノールが含まれている食品だからといってカフェインやアルコールの過剰摂取にならないよう注意しましょう。
ポリフェノール以外にも、認知症対策への効果が期待できる成分は数多く存在します。認知症対策に効果的な食べ物や最適な食事方法については、こちらの記事で詳しく解説しています。
👉認知症予防に効果的な食べ物は? 最適な食事方法や食材を紹介 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
嗜好品が健康サポートの強い味方に
ポリフェノールにはカテキン、イソフラボン、アントシアニンなど、さまざまな種類があり、普段口にしている食品に数多く含まれています。例えば、コーヒー・緑茶・赤ワイン・チョコレートなど。いずれも嗜好品と呼ばれるものですが、日々の食事に気を使っている方もときには嗜好品を上手に取り入れることで、ポリフェノールの恩恵を受けられるでしょう。
しかし、ポリフェノールの摂取だけにとらわれて、過剰に食べ過ぎたり飲み過ぎたりするのは禁物。それぞれの飲料や食材における適量を心がけることが大切です。
編集:はてな編集部
編集協力:株式会社エクスライト
ポリフェノールを多く含む嗜好品などを日常的にどれくらい摂取するべきか、食事とのバランスをどうすべきか、考えてしまう方もいるでしょう。「食生活の改善方法が分からない」「一人では健康的な食生活を続けられる自信がない」という人は、プロに頼ってみてもよいかもしれません。
フォーネスライフが提供する疾病リスク予測サービス「フォーネスビジュアス」では、20年・5年以内(※5年以内は65歳以上が対象)の認知症をはじめとした各種疾病のリスクを予測できます。さらに、結果に応じてコンシェルジュ(保健師)が生活習慣改善方法をご提案するので、自分に合った食事内容の改善ができます。 ※フォーネスビジュアス検査は、医療機関の医師を通じて提供します。認知症のリスク、調べてみませんか?
*1:参考:国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「すこやかな高齢期をめざして No. 46『緑茶にする?コーヒーにする? ~認知機能との関連性~』」
*2:参考:河野洋一・藤田和弘「コーヒー豆中のクロロゲン酸類と総ポリフェノールの分析」(2016)[PDF]
*3:参考:国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「すこやかな高齢期をめざして No. 46『緑茶にする?コーヒーにする? ~認知機能との関連性~』」
*4:参考:新潟大学医学部医学科「日本人高齢者におけるコーヒー、緑茶、カフェインと認知症リスクの関連」
*5:参考:下方浩史「認知症の要因と予防」(2015)[PDF]
*6:参考:日本農芸化学会「カカオポリフェノールの包括的研究」(2018)[PDF]
*7:参考:蒲郡市「チョコレートの摂取による健康効果に関する実証研究 中間報告」


 詳しく見る
詳しく見る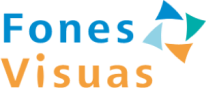
 「フォーネスビジュアス」のサイトを見る
「フォーネスビジュアス」のサイトを見る