
肥満は生活習慣病などの疾患のリスクを高めることが知られています。では、肥満を含む体重の変化と認知機能にはどのような関係があるのでしょうか。肥満と認知症の関係や認知症発症リスク、肥満の予防について解説します。
こんな人におすすめ
- 体重と認知症の関連に興味がある人
- 自分や家族の太りすぎを心配し、認知症発症リスクが高まるのかどうか不安に感じている人
- 肥満によってどのような健康リスクがあるのか調べている人
肥満の人は認知症になりやすい?
肥満とは、単に体重が多いことを指すのではなく、脂肪組織に脂肪が過剰に蓄積した状態で、BMI(Body Mass Index:体格指数)が25以上の場合を指します。BMIは国際的な標準指標として用いられており、[体重(kg)]÷[身長(m)2 ]で計算できます。BMIの標準は男女ともに22.0とされています*1。
肥満は、認知症のなりやすさに関連しているといわれています。どのような関連があるのでしょうか。
中年期の肥満で認知症発症リスクが増加
中年期(40〜64歳)では特に、太っているほど認知症になりやすくなると考えられています*2。そのため、中年期の肥満を防ぐことが認知症対策につながる可能性が示唆されています。さらに、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病が認知症の発症リスクを増加させることが知られており、肥満はそれらの疾患の原因にもなります*3。そのため、肥満自体に気をつけることはもちろん、肥満などを要因とした生活習慣病を予防することも大切です。
肥満の人は脳が10年早く老化する?
ケンブリッジ大学が主導した研究では、肥満や過体重の人は、やせた人に比べて、脳の「白質」という場所の神経細胞の減少が認められました。それにより、肥満・過体重の人の脳はそうでない人の脳よりも約10年老化が早くなると報告されています*4。肥満を予防し、認知症になりにくくする生活のコツとは

認知症対策には食生活や運動習慣などの生活習慣改善が有効であると考えられていますが、それは肥満を予防する上でも大事な視点です。どのようなことに気を付ければよいのでしょうか。
バランスのよい食生活を心がける
認知症対策のためには、1日3食、バランスよく食べることが重要だといわれています*5。また、バランスのよい食生活は、肥満の防止にもつながります。肥満を防ぐためには、摂取カロリーや食事量を適切に保つ必要があります。ただし、1日に必要な摂取カロリーは年齢や体格、性別、身体活動レベルによって異なります。必要な摂取カロリーは、日本医師会の「推定エネルギー必要量」で調べることができますので、自分や家族に必要なエネルギー量を知り、適切な食事の内容や量に生かしましょう。
認知症対策のための食事に関する情報については、下記の記事も参考にしてください。
👉認知症予防に効果的な食べ物は? 最適な食事方法や食材を紹介 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
お酒の飲み過ぎに注意する
肥満を防ぐためには、食べ物だけでなくアルコールの摂取量にも注意が必要です。食べ物や飲み物のカロリーはもちろん、アルコール自体のカロリーも意識しましょう。アルコールは、1gで約7kcalある高カロリー物質です*6。たとえ糖質ゼロのアルコール飲料を選んだとしても、アルコールのカロリーは無視できません。9%の缶チューハイ500mlなら、アルコール分だけで約250kcalを摂取することになります。
厚生労働省の「健康日本21(第二次)」では、生活習慣病のリスクの高い飲酒量を、男性1日平均40g以上、女性20g以上(純アルコール量換算)と定めています。純アルコール20gは、ビールで換算すれば500ml(ロング缶1本)、日本酒なら1合(180ml)、ワインならグラス2杯弱(200ml)です。 また、大量の飲酒をする人は認知症になりやすくなるという報告もあります*7。適切な飲酒量を守ることが必要です。
認知症とアルコールの関連性について詳しく知りたい方は、下記の記事も参考にしてみてください。
👉認知症とアルコールの関係は? リスクを高める飲酒量について解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
適度な運動習慣を身につける
運動不足が認知機能の低下や認知症の発症に関連することが知られています。定期的な運動(週3回・週2時間以上)をしていた人は、そうでない人に比べて、5年後の認知症のリスクが約3割低くなるという報告もあります*8。さらに、肥満を予防する観点からも、定期的な運動やトレーニングは欠かせません。認知症と運動の関連性やおすすめのトレーニング習慣について、下記の記事で詳細に解説しています。詳しく知りたい方はこちらも参考にしてみてください。
👉認知症はトレーニングで予防。今日から始める運動習慣で認知症のリスクを軽減しよう - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
認知症の発症因子となりうる肥満を予防しよう
肥満は、それ自体が認知症の発症リスクを高め、認知症発症に関連するといわれる生活習慣病の要因ともなります。食生活や運動習慣などを見直して、特に中年期の肥満を予防しましょう。
また、生活習慣の改善は、認知機能低下の抑制に貢献するともいわれています。生活習慣を見直して、心身ともに健康に暮らせるよう努めましょう。
編集:はてな編集部
編集協力:株式会社エクスライト
フォーネスライフが提供する疾病リスク予測サービス「フォーネスビジュアス」では、20年・5年以内(※5年以内は65歳以上が対象)の認知症をはじめとした各種疾病の将来の発症リスクを予測できます。さらには結果を踏まえて、コンシェルジュ(保健師)がご自身に合った生活習慣改善方法をご提案。自分ではなかなか改善しにくい食生活や運動習慣などについてアドバイスを受け、実践することで、各種疾病対策や肥満の解消にもつながります。
※フォーネスビジュアス検査は、医療機関の医師を通じて提供します。認知症のリスク、調べてみませんか?
*2:参考:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」[PDF]
*3:参考:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」[PDF]
*4:参考:Ronan, L et al. Obesity associated with increased brain-age from mid-life. Neurobiology of Aging; e-pub 27 July 2016; DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2016.07.010
*5:参考:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」[PDF]
*6:参考:e-ヘルスネット「アルコールとメタボリックシンドローム」
*8:参考:国立研究開発法人 国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック」[PDF]


 詳しく見る
詳しく見る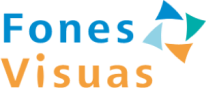
 「フォーネスビジュアス」のサイトを見る
「フォーネスビジュアス」のサイトを見る