
認知症になりやすい人には、普段の言動に特定の傾向が見られるという説があります。
本記事では、言動にどんな傾向が見られると認知症になりやすいのか、注意しておきたい口癖や生活習慣などを紹介します。認知症になりにくい生活習慣を取り入れていくことで、将来的な予防にもつながります。
こんな人におすすめ
- 自分が認知症になりやすいかどうかを知りたい人
- 予防したいと考えており、自分で対応策を調べている人
- 予防につながる考え方や生活習慣を知りたい人
認知症になりやすい人の口癖とは
まずは、認知症になりやすい人の口癖を見ていきましょう。一例ではありますが、下記のような発言が増えてきた場合、注意が必要かもしれません。
- 「仕事が忙し過ぎてゆっくり食事もできない」
- 「何をしても面白くない」
- 「何もしたくない」
- 「面倒くさい」
- 「イライラする」
- 「腹が立って仕方がない」
- 「何を食べてもおいしくない」
- 「固いものは食べたくない」
- 「もっと大きな声で言って」
- 「よく聞こえない、分からない」
- 「寂しい」
- 「自分は孤独だ」
こうした口癖がある人は、なぜ認知症を発症する可能性が高いのでしょうか。これらの背景にある要因を次項以降で解説します。
なりやすい人の特徴

口癖は、そのときの本人の状態を表していることがあります。ここでは、前述した口癖をよく言う人がどのような状態にあるのか、なぜ認知症になりやすいのかをひも解いていきます。ただし、こうした人が必ず発症するというわけではないので、あくまで目安と考えてください。
仕事が忙しい・生活が不規則
「仕事が忙しくてゆっくり食事もできない」といった発言が多い場合、時間に追われて不規則な生活になり、食生活がおろそかになっている可能性があります。乱れた食事や運動不足、睡眠不足は認知症の発症リスクを高めると言われており*1、口癖になるほど忙しい状態が継続している場合、注意が必要です。
意欲が低下している・抑うつ的になっている
「何をしても面白くない」「何もしたくない」「面倒くさい」という発言から考えられる意欲低下や抑うつ状態は、認知症の兆候の一つです*2。特に65歳以上の人で、このような状態が続く場合、認知症の前触れと判断されることがあります。
ただし、周囲がその状態を改善しようとして「そんなことを言わずに頑張って」と無理やり意欲を引き出そうとするのは逆効果になることも。「元気な人だったのに、急に何もしなくなった」「以前よりも目に見えて意欲が低下している」などと心配になったら、無理に本人を変えようとせず、医療機関に相談してみてください。
怒りっぽくなってきた
もともと穏やかだった人が急にイライラしだしたり、多少怒りっぽいところがあった人が以前にも増して頭に血が上りやすくなったりした場合、認知症の兆候である可能性があります*3。
大事なのは、生まれ持った性格に焦点を当てるのではなく、「最近になって怒りっぽくなった」という傾向を見逃さないこと。「イライラする」「腹が立って仕方がない」という発言が前よりも目立つようになったら注意しましょう。
口腔に問題がある
残存する歯の本数が多い、あるいは入れ歯などで適切な口腔状態が保てている人は、認知症になりにくい傾向があります*4。逆に、口腔状態が悪化している人は注意が必要です。
また、歯周病菌がアルツハイマー病と関連するという報告も。「何を食べてもおいしくない」「固いものは食べたくない」という言葉には、口腔内の問題が隠れていることがあるので気をつけておきましょう。
耳が聞こえにくい
「もっと大きな声で言って」「よく聞こえない、分からない」という発言が増えた場合、加齢による難聴の可能性が考えられます。聞こえにくい状態が続くと、生活の質が下がり、人との交流が減ったり、孤独や抑うつをもたらしたりして、認知症の発症リスクを高めると考えられます*5。
社会的に孤立している
人との交流が少なくなると、認知症発症の可能性が高まることが分かっています*6。「寂しい」といった弱気な発言や「自分は孤独だ」という口癖が見られた際、会話の機会を増やしたり、社会活動に参加したりして人との交流を増やし、孤立感を緩和することで改善につながる場合があります。
なりにくい人の特徴

続いて、認知症の発症リスクが低いと言われる人の特徴や傾向を紹介します。
以下のような特徴のある人は、確かに認知症になりにくいかもしれませんが、それは持って生まれた性質であったり、本人が積極的にそうしようと思っていたりする場合も考えられます。元々そうでない人が無理に変えようとしてもストレスがかかるばかりで、かえって認知症をはじめとする疾病リスクを高めてしまうことも。何より大切なのは、本人が無理なく、自分らしく過ごせることです。
開放的・おおらか
開放的でおおらかな人は、細かいことを気にせずどっしり構えられる人が多いものです。そのため、閉塞的で悩みごとが多い人よりも認知症になりにくい傾向があると考えられています。
人付き合いが好き
人と話すのが好きな人、人と一緒に何かをするのが得意な人は、他者との会話や大人数での食事などの機会が多くなります。コミュニケーション量が多い人ほど、認知機能が低下しにくい*7と考えられており、他人とよく接する人ほど認知症の発症リスクが低いと言えるでしょう。
真面目・勤勉
真面目で勤勉な人は、認知機能の低下を感じたときにきちんと対処しようとするので、それ以上の認知機能低下を抑制することが報告されています。また、規則正しい生活習慣を維持しようとする人が多いので、生活習慣の乱れによる発症リスクが低減しやすいと考えられています*8。
周囲の意見や新しい情報を取り入れる
周囲の声に耳を傾けたり、必要な情報を探して取り入れようとしたりする人は、認知症になりにくい傾向があるようです。しっかり情報収集を行って将来的なリスクを知り、適切な予防策を取り入れることで、発症の可能性を下げることができます。
なりやすい人の生活習慣

認知症の発症リスクには、普段の生活習慣も深く関わっていると言われています。ここでは、認知症になりやすい人の主な生活習慣を見ていきましょう。
食生活が乱れている
食生活が乱れていると、必要な栄養がとれず、認知症を発症しやすくなる可能性があります。中でも、飽和脂肪酸を多く含む肉類や脂身、マーガリンなどを多く摂取したり、野菜や果物をあまり食べなかったりする生活は注意が必要です。塩分や糖質が多過ぎる食事にも気をつけましょう。
飲酒量が多い
アルコール依存症の人には、高い割合で脳萎縮が見られます。350mlのビールを週に7本以上飲む人の認知症発症リスクは、まったく飲酒しない人の約1.5倍、14本以上飲む人は約2.5倍になるという報告*9も。また、飲酒量が多いと生活習慣病を引き起こし、認知症発症の引き金になることがあります。お酒を飲む場合は1日に350mlのビール1本程度にとどめ、週に1日以上の休肝日を設けるようにしましょう*10。
運動不足
運動不足で筋肉量が減るのに伴って活動量が減り、運動や外出などから得られる刺激が少なくなると、認知機能が低下しやすいと考えられています。また、運動不足の人は肥満や糖尿病、高血圧などの生活習慣病にかかりやすくなり、その結果として認知症の発症リスクを高めてしまいます。
睡眠不足
アルツハイマー病の原因となるタンパク質の産生・排出には、睡眠不足が関わっているという報告があります。必要な睡眠時間は人によって異なりますが、5〜6時間以下の睡眠が習慣になっている人は注意しましょう。
認知症と睡眠の関係については下記の記事もご覧ください。
👉認知症と睡眠は関連がある? 発症や症状への影響と改善方法を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
高齢者の一人暮らし
一人暮らしで人との会話が少なくなると、外部からの刺激が減り、認知機能が低下しやすくなると言われています。また、高齢者の一人暮らしでは孤食が多いことから、食事のバランスが崩れたり、食事から得られる刺激が少なくなったりと、食生活にも悪い影響をもたらすことがあります。
認知症を予防するには

では、認知症を予防するためにはどうすれば良いのでしょうか。ここでは、認知症予防に効果的だとされている方法を紹介します。
規則正しい生活を心掛ける
バランスの良い食生活や運動習慣、睡眠習慣を整えることが認知症予防につながります。バランスのとれた食事を心掛け、タンパク質、炭水化物、脂質、食物繊維、ビタミン類などの栄養素をバランスよく摂取することが有効です。また、ウォーキングやジョギングといった週3日以上の有酸素運動もおすすめです。
人との交流を積極的に持つ
家族や友人との会話、外出頻度などが多い人は、認知症になりにくいと言われています。周囲とのつながり(社会的ネットワーク)を十分に持ち、人との交流を積極的に行うことが認知症予防につながります。
基礎疾患を治療する
糖尿病や高血圧といった生活習慣病、歯周病などが認知症の発症や進行に関わっていることが分かっています。こうした基礎疾患を放置せず、きちんと治療することも認知症予防の一つです。
認知症対策のために気をつけたい生活習慣については、下記の記事もあわせてご覧ください。
👉認知症になりやすい人の特徴は? 注意したい生活習慣、予防策を紹介 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
👉認知症の予防は何歳からやるべき? 発症リスクを高める要因と効果的な対策を紹介 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
👉認知症予防に脳トレを取り入れよう。期待できるメリットとおすすめのトレーニング方法 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
口癖に発症の要因が隠れていないか確認しよう
認知症になりやすい人の言動には、生活習慣や疾患が隠れていることがあります。自分や家族の言動や行動に気をつけ、認知症リスクを高める要因がないかをチェックしてみましょう。家族みんなで生活習慣改善、疾患の治療などに取り組むことで、中途半端に止めてしまうということも防げるかもしれません。
また、最近生じるようになった怒りっぽさや意欲低下は本人の性格によるものではなく、認知症の前触れであることも考えられます。本人の個性を尊重しつつ、気になることがあれば医療機関に相談してみましょう。
編集:はてな編集部
編集協力:株式会社エクスライト
認知症の発症リスクが気になっているなら、フォーネスライフが提供する疾病リスク予測サービス「フォーネスビジュアス」を活用するのも1つの手段です。フォーネスビジュアスは、20年・5年以内(※5年以内は65歳以上が対象)の認知症をはじめとした各種疾病について、将来の発症リスクを予測し、その結果を踏まえてコンシェルジュ(保健師)が個々の生活習慣の改善方法をご提案します。自分では難しい食生活や運動習慣の改善をプロと一緒に進められますので、認知症になりにくい生活を実現するために、ご家族で検討してみてはいかがでしょうか。
認知症のリスク、調べてみませんか?
*1:参考:国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック [PDF]」
*2:参考:国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック [PDF]」
*3:参考:厚生労働省「認知症ケア法-認知症の理解 [PDF]」
*4:参考:日本歯科衛生士会「認知症の予防には歯周病予防対策を! [PDF]」(歯とお口の健康情報 2023年2月1日)
*5:参考:国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック [PDF]」
*6:参考:国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック [PDF]」
*7:参考:国立研究開発法人国立長寿医療研究センター「あたまとからだを元気にするMCIハンドブック [PDF]」
*8:参考:「Personality and global cognitive decline in Japanese community-dwelling elderly people: A 10-year longitudinal study(日本の地域在住高齢者の性格と全体的な認知機能低下:10年間の縦断研究)」(PubMed)、「施設介護職員による認知症高齢者の性格・感情認知とケア・対処方略の関連」(岩手大学リポジトリ)
*9:参考:Mukamal KJ, Kuller LH, Fitzpatrick AL et al.Prospective study of alcohol consumption and risk of dementia in older adults.JAMA, 289:1405-1413, 2003.
*10:参考:e-ヘルスネット(厚生労働省)「アルコールと認知症」


 詳しく見る
詳しく見る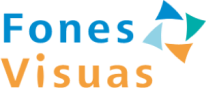
 「フォーネスビジュアス」のサイトを見る
「フォーネスビジュアス」のサイトを見る