
仕事におけるプロジェクトでさまざまな問題が起こり、現場のメンバーが心身共に追い詰められてしまうことは珍しくありません。
上司やマネージャーが舵取りを誤って状況が悪化してしまうことも多くあり、中には悪気なくメンバーを追い込んでしまうマネージャーも存在します。メンバーとしては、そんな“人を壊すマネジメント”から、どのように身を守ればいいのでしょうか。
今回お話を聞いたのは、2025年3月の刊行から話題となっているビジネス書『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン50』の著者であり、数百件のプロジェクトに携わってきた橋本将功さん。
「壊してくるマネージャー」への対処法と、自分自身を守るための心構え・セルフケアの具体策を伺いました。
目次
チームの中で人が“壊れる”前に気付くためのポイントは?

──橋本さんの著書『人が壊れるマネジメント プロジェクトを始める前に知っておきたいアンチパターン50』では、適切でないマネジメントによりメンバーが壊れてしまうさまざまなケースが紹介されています。メンバーの立場として、周囲の人が壊れる兆候を早く発見し対応するためには、どのようなサインに注意すべきでしょうか。
橋本将功さん(以下、橋本):忙しいと、つい仕事の中身に集中してしまいがちです。しかしどんな状況であっても、目の前にいるのは「人」であるということを意識しておく必要があります。
例えば、その人の表情や言葉などに注意を払うことで、大変な状況になっていないか、冷静さを保てているかなどに気を配る。これはコミュニケーションの基本でもあります。
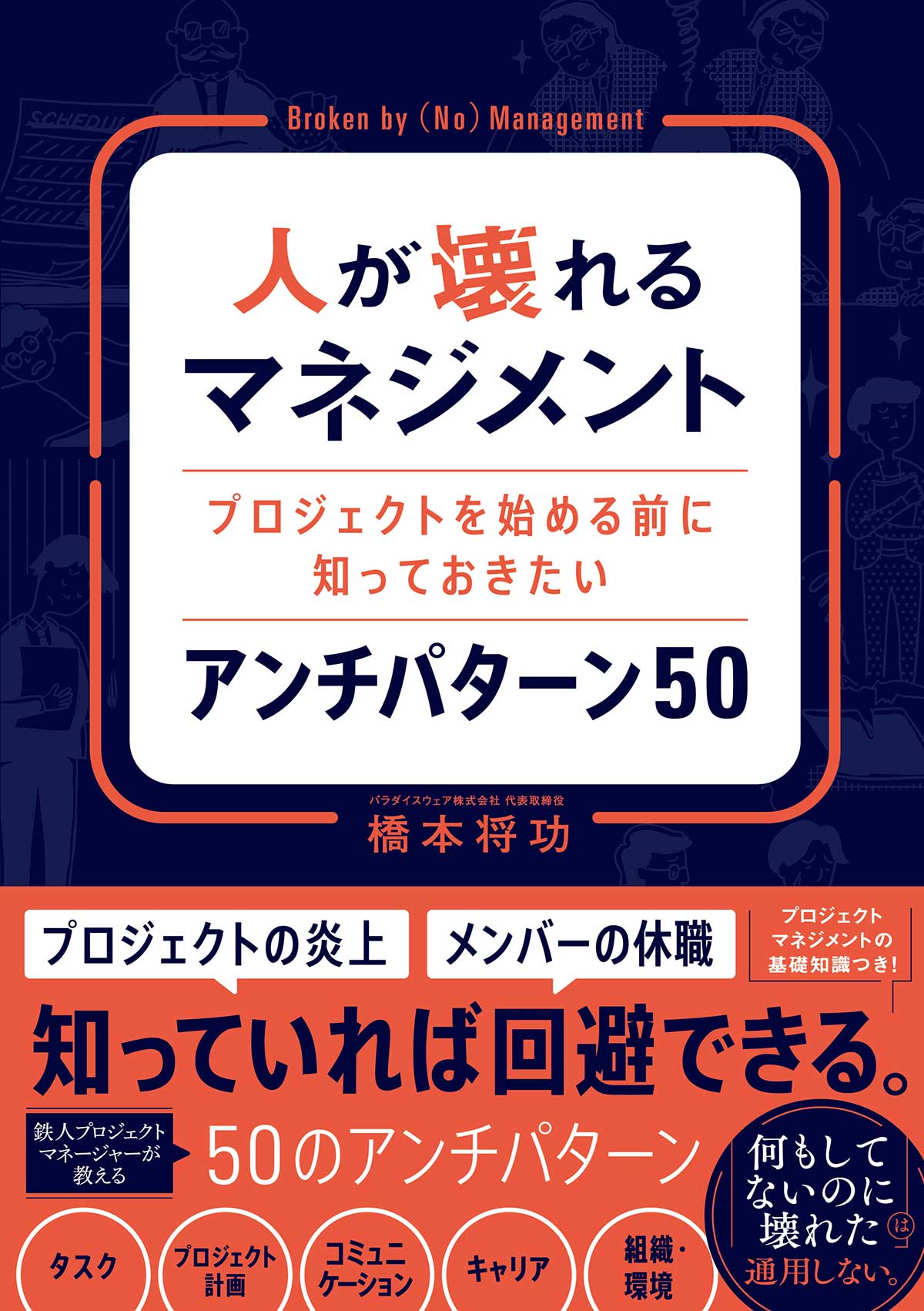
(橋本将功 著、ソシム)
──確かに著書でも「マイクロマネジメントが原因でメンバーが指示待ち状態になる」というケースが描かれていました。その人の変化に注意することで、“壊れる”サインに気付ける可能性がありそうです。
橋本:そうですね。こういったご時世なので、どこまで相手の事情に踏み込んでいいかは議論があるところです。ただ、やはり一緒に仕事をしている仲間ですから、気にかけることは大切です。
例えば、以前は「休みの日にあそこへ出かけた」「この前見たこんな映画が面白かった」というような仕事以外の話も気軽にできていたのに、そういった会話が極端に減っているようなケース。
他にも、仕事がすごく忙しい状況でもないのに疲れて見えたり、追い詰められていたりするようだと、プライベートも含め何か問題を抱えている可能性があります。
その場合は仕事を肩代わりする提案をしたり、場合によってはリーダー的な立ち位置の人に相談したりするといいでしょう。
──そうしたサポートが行えるようなチームであることも重要ですね。
橋本:はい。チームの状態については、打ち合わせなどで率直な意見が出るかどうかで分かります。
思いつきや新しい意見はチームの状態によっては否定されることも少なくありませんが、ちゃんと出るということは、心理的安全性(自分の考えや気持ちを安心して話せる状態)が確保されている証拠です。
逆に「上司が言うことをメンバーが黙って聞いて従うだけ」になっているチームは、改善の必要があるといえるでしょう。
またリモートワークの場合は、カメラをオフにしていることが、チームの状況を表すサインになっている場合もあります。表情を見せないのは、自分の世界に閉じこもってしまっている可能性があるんです。
入ってきたばかりの人にとっては、チーム自体の心理的安全性が高くても、リモートワークが多い状況で中に入っていけず孤独感を覚えてしまうことがあります。つぶれる前にサインに気付き、ケアすることが大切です。
──そのためには、普段からチームでコミュニケーションをしっかり取ることが重要ですよね。
橋本:そうですね。例えば私がよくやっているのは、定例会議の終わりにメンバーを指名して、最近起きた出来事や面白かったことについて話してもらうやり方です。
各メンバーが自分の話をするだけなので、他の人が踏み込み過ぎることはありません。聞いている側はその人の人となりが分かるので、コミュニケーションの円滑化にも効果的だと感じています。
自分自身が“壊れそう”なサインに気付くには

──周りのメンバーではなく、自分自身が“壊れる”前に気付くためのポイントはあるでしょうか。
橋本:人によってサインは異なりますが、例えば私自身の場合だと、外出の機会が減ったり考え事が増えたりすると、あまりよくない状態だと判断するようにしています。
多くの人に当てはまるサインとしては「好きなことができなくなる」と危ないと感じますね。
「最近ゲームやってないな」とか「外にごはんを食べに行っていないな」とか、本来好きだったことができていないのは、心が弱っているサインの可能性があると考えています。
──そうした自分自身の危険な兆候に気付いたら、どのように対処すればいいでしょうか。
橋本:まず重要なのは、自責の念にとらわれないことです。
日本人は特に、うまくいかないときに自分自身を責めがちです。会社や上司から評価を得られないときなどに「自分がダメなんだ」と思ってしまう。キャリアが浅いと、特にそう思ってしまいます。
ですが、実際には自分ではなく組織やマネージャーの評価の方が間違っていることだって多々あります。ですから、できるだけ状況を俯瞰(ふかん)して見るように心掛けてほしいです。
問題のある上司には、適切なプロセスを踏んで対処を

──その上で、問題を抱える上司やマネージャーにはどのように対応すればいいでしょうか。
橋本:これまでに私が見てきたケースでいうと、問題のあるマネジメントをする上司って、必ずしも悪意を持っているわけではないんです。本人はよかれと思ってやっていることも少なくありません。
ですから、上司のマネジメントで自分が壊れそうになったときは、できればまず、上司本人に意図を確認することをおすすめします。
ただ、それもできないくらいにメンタルがやられてしまっている場合や、確認しても上司が変わらない場合、明らかに悪意を感じるような場合などは、人事部やさらに上の上司に相談して、配置転換などを希望するといいでしょう。
ここで大事なのは、プロセスをしっかりと踏むことです。直属の上司に確認しないまま、いきなり上司の上司に掛け合うのは、あまり得策ではありません。
正しいプロセスを踏んで相談し、それでも状況が変わらなければ、その会社に見切りをつけることも選択肢に入れていいと思います。
──然るべき窓口への相談や、配置転換、あるいは転職といった方法は「環境自体を変える」根本的な解決策かと思います。他に、仕事で「これをやっておくと“人を壊すマネジメント”に対応できる」というポイントはあるでしょうか。
橋本:自分の身を守るという点では「記録を取る」ことがとても重要です。
仕事をしていると、いろいろな人と出会います。中には他者の手柄を横取りする人もいるし、自分の悪評価から逃れるために他者に責任を押し付ける人もいる。
そういう人と関わってしまって被害を受けないためには、タスクや会議などの記録を取っておくことが大事なんです。私自身も、それで助かった経験が何度かあります。
──自衛のためだけでなく、仕事をする上でも記録は大事ですよね。
橋本:そうですね、クライアントワークでも“言った言わない”でトラブルになることもありますから。それに、記録が残っているというだけで、問題行動を起こさなくなる人もいます。
私は企業の研修でも必ず「仕事では記録を取るようにしてください」と伝えています。
──そのほか、仕事で負荷がかかっている場合に、私生活の中でうまくセルフケアする方法があれば教えてください。
橋本:私自身は、自分をケアする「行動習慣」を持っておくことで、ストレスレベルを下げるようにしています。
会社員時代には、どんなにプロジェクトが大変でも、必ず昼食を外で食べるようにしていました。その行動習慣が気分転換になり、自分自身のメンタルを守ることにつながっていたんです。
プロジェクトが忙しいと、昼食を社内でサッと済ませたり、あるいは食べること自体を諦めたりするようになりがちです。でもそうやって行動習慣を破ると、どんどん追い詰められていき、結果的にパフォーマンスの低下にもつながりかねません。
行動習慣は何でも構いませんが、できるだけ守りやすく、自分のモチベーションにつながるようなものがいいでしょう。
──確かに、自分で決めた行動習慣を守ることで、自分自身のコントロールを失わずに済む気がします。
橋本:そうですね。ちなみに仕事が忙しいと、どうしても余った時間を睡眠に充てたくなりますよね。でも私の場合は、睡眠時間を多少削ってでもそうした行動習慣を守った方が、精神が安定する印象がありました。
私の妻は、寝る前に必ず作業ゲーム(アイテム収集などの単純な作業や繰り返しの操作を主体とするゲーム)で遊んでいます。シンプルな作業を繰り返すことで、リラックスできているようです。
もちろん健康状態は気にかけつつ、トータルで考えて自分が最もリラックスできる方法を見つけるのがいいんじゃないかと思います。
時には「やりたい仕事で評価されたい」という考えを捨てることも必要

──これまで数多くのプロジェクトをご覧になってきた橋本さんですが、実際に「人が壊れる」場面に遭遇したり、アドバイスしたりしたエピソードを教えてください。
橋本:プロジェクトで人が壊れるときに多いケースとして「時間が限られている中でパフォーマンスを上げる必要に迫られる」というものがあります。
さらに、ポジションチェンジやチームのマネジメントといった「新しい役割が与えられたとき」が重なると、かなり厳しくなることはありますね。
そういった状況に陥っている人に対しては、新しいポジションや動き方に対する考え方についてアドバイスすることが多いです。それは成長につながるいい悩みなんだよと伝え、その上でどう考えればいいのかをアドバイスする。
──考え方を転換することで、救われる場合もありそうですね。ただ、それでも「周りに迷惑をかけたくない」とか「嫌われたくない」といった考えにとらわれて、がまんしてしまうこともあるかもしれません。
橋本:そこについては「やりたい仕事で評価を求めない」という考えが、時には大事なのではないかと思っています。
評価というのは「評価する人」によっても変わるし、そもそも「自分がその仕事に合っているかどうか」にも左右されます。
例えば、私はもともとソフトウェアエンジニアになりたかったんです。ただ、ソースコードを書く仕事では周りには自分よりも優秀な人がたくさんいた。そこで周りがやらないような仕事や、周りから評価されるような仕事を続けてきたら、いつのまにかその仕事に「プロジェクトマネジメント」という名前が付いていました。
「自分がやりたい仕事を続けないといけない、評価を得なければいけない」という考えを捨てることで、我慢してストレスを溜め込むことがなくなるケースもあると思います。
──ここでも先ほどおっしゃっていた「客観視」が役立ちそうですね。
橋本:はい。四半期に一度会社に評価されて、年に一度ボーナスの査定をされる。そういうイベントを一種のゲームとして捉え、今の仕事を自分がどう感じているのか見つめ直す機会にすることで、自分自身が壊れるのを防ぐ。
例えば、本来向いていないはずの仕事で一時的に評価され、その方向に進んでしまったりする方が大変だと思いますよ。ポジションが上がってからキャリアを修正するのは簡単ではないですから。なので30代までは、さまざまな選択肢を考えてキャリアを歩むのがいいと思います。
──今後、マネジメントで壊されないような働き方を実現するために、どのようなことを意識しておくといいでしょうか。
橋本:大事なのは、キャリアを長距離走と捉えることです。
例えばフルマラソンでも、42.195kmを走り切ろうと思ったら、いくら最初のラップタイムが速くても意味がないですよね。逆にしんどくなって、リタイアしてしまう可能性もある。
合わない仕事に全力を注いで疲弊したり、人を壊すマネジメントでつぶれてしまったりするのは、それと同じなんです。
合わない上司や組織に運悪く当たってしまっても、それはキャリア全体から見ればほんの一部。自分自身がどういうレースをしたいのかを考えて、改善に向けて取り組んだり、時には組織や環境自体を見直すという考え方も重要だと思います。

取材・構成:山田井ユウキ
撮影:関口佳代
編集:はてな編集部
今回は橋本さんに、自分のメンタルを守りながら働くためのヒントを伺いました。
心身のセルフケアを考える上では、日々の「生活習慣」を整えることも重要なポイントです。
フォーネスライフが提供する疾病リスク予測サービス「フォーネスビジュアス」では、“今”と“将来”の健康状態と疾病リスクを可視化し、保健師の資格を持つコンシェルジュから生活習慣改善のアドバイスを受けることができます。フォーネスビジュアスについて、詳しくは下記の記事をご覧ください。
あなたの生活習慣改善を、専門家がサポートします




 詳しく見る
詳しく見る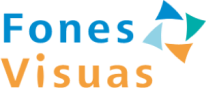
 「フォーネスビジュアス」のサイトを見る
「フォーネスビジュアス」のサイトを見る