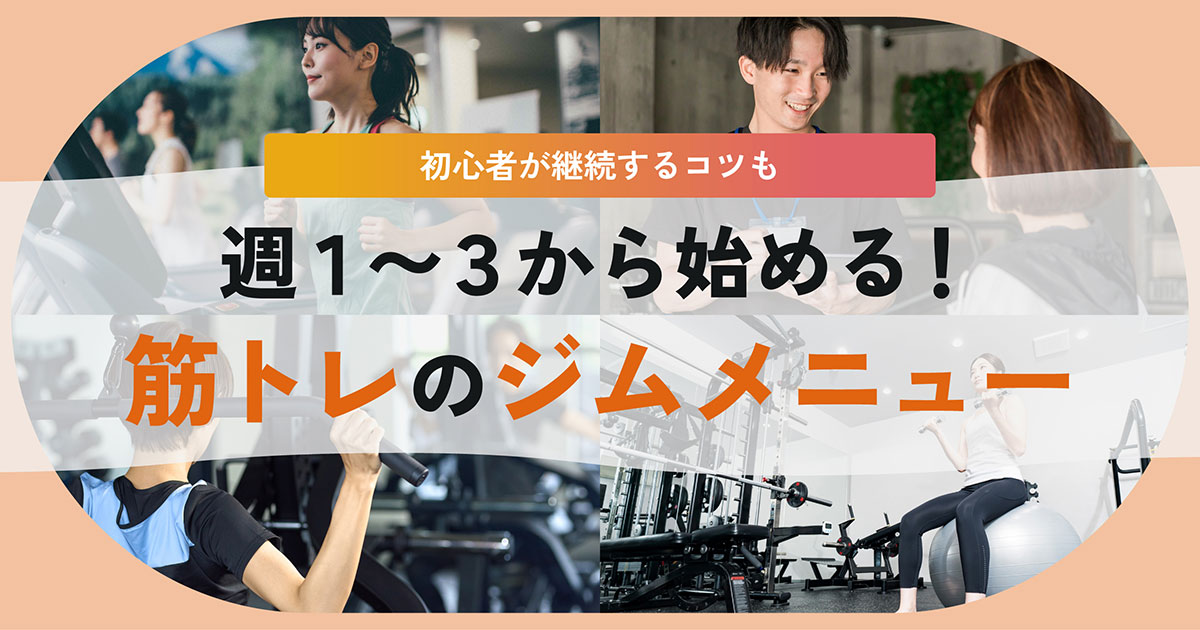
筋トレをする上で、ジムでのメニューはどんなものが適切なのでしょうか? ジムに入会したものの「何をすれば効果的なのか分からない」「継続が難しそう」と不安になる方もいるでしょう。
本記事では「週3日」通うことを前提とした初心者でも運動を続けるコツや、1週間のおすすめメニューをまとめました。さらには「週1〜2日」通う場合のポイントも紹介します。
疲れにくく動ける身体を目指して、まずは3カ月続けることを目標にしましょう。
目次
なぜ“週3ジム通い”が最適なのか?
負荷をかけた筋肉が回復するまでのサイクルを考えると、ジム通いは「週3回」のペースが理想になります。
筋トレ(筋力トレーニング)によってダメージを受けた筋肉の繊維は、その後の栄養摂取と休息によって、より強く太くなろうとします。この現象は「超回復」と呼ばれており、筋肉の部位にもよりますが、一般的には48〜72時間程度の休息が必要とされています。
「超回復」については下記の記事で詳しく解説しています。
筋肉痛のとき筋トレしてもいい?痛みの程度別の対処法と回復法を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
超回復のサイクルを考慮した場合、毎日同じ筋肉に負荷をかけるトレーニングでは、十分な休息期間を確保できません。筋肉の回復前に負荷をかけ過ぎると、オーバートレーニングでケガをする可能性も考えられます。
週3回のペースであれば「1日おき」または「2日おき」のトレーニングになるため、十分な休息期間を確保できます。理想的な頻度はトレーニング経験や目的によっても変わりますが、効率的に身体を鍛えたい方は「週3回」を目安にしてみましょう。
厚生労働省の「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」でも、成人については週150分以上の中強度の身体活動が推奨されています。週3回のジム通いを想定すると、1日あたり60分のトレーニングで十分にカバーできるため、健康維持の観点からも「週3ジム通い」は理想的な頻度です。
週1〜2回しかジムに通えない場合は?
ジムに通える頻度が週1〜2回の方には「全身法」と呼ばれるメニューがおすすめです。全身法は一度に多くの筋肉をバランスよく鍛える方法で、トレーニングの頻度が少ない方でも、各部位の超回復に必要な負荷をかけられます。
まずは、胸・背中・脚といった大きな筋肉を中心に「各部位1〜2種目」を目安にして、基本的なマシンや自重を使ったトレーニングに挑戦してみましょう。
週3ジム通いのトレーニング時間は? 基本の考え方
筋トレの初心者にとって、週3回のジム通いは簡単ではありません。トレーニングを習慣化するには、無理のないペースで身体作りを目指すことが大切です。以下では、週3回のトレーニングを無理なく続けるための考え方や、効果的に行う準備について解説します。
トレーニング時間は60〜90分が目安
ジムでのトレーニング時間は、1回あたり60〜90分を目安にしましょう。この時間には、ウォーミングアップやメイントレーニング、クールダウンの時間も含まれます。
トレーニングを始めたばかりの初心者には、十分な体力や集中力が備わっていません。無理をすると思わぬケガにもつながるため、初めは60分程度から始める方法がおすすめです。
トレーニングで大切なことは、時間よりも内容の質です。正しいフォームで各種目を丁寧にこなし、筋肉に適度な刺激を与えることを意識しましょう。体力がついて慣れてきたら、徐々にトレーニング時間を延ばし、種目数を増やしていきます。
自身の身体と相談しながら、コンディションに合わせてメニューを調整することも大切です。「今日は少し疲れている」と感じたら、トレーニング時間や負荷を抑えることも考えましょう。
トレーニング前後のストレッチで安全性と効果を高める
ケガを予防しつつ効果を高めるには、トレーニング前のウォーミングアップ(準備運動)と、トレーニング後のクールダウン(整理運動)を取り入れることが大切です。
ウォーミングアップについては、体温を上げながら筋肉や関節を動かしやすくし、心肺機能を徐々に高める効果が期待できます。
バイクマシンやトレッドミル(ウォーキングマシン)などを使い、5〜10分程度で軽く汗ばむくらいの有酸素運動をこなしましょう。肩回しや股関節回し、軽い屈伸運動などの動的ストレッチを取り入れると、関節の可動域が広がるため、トレーニングの安全性や効果を高めやすくなります*1。
一方で、クールダウンは興奮した神経を鎮めて、少しずつ心拍数を平常に戻し、疲労した筋肉の回復を促すために行います。負荷をかけた筋肉を中心に、5〜10分程度の静的ストレッチを取り入れましょう。ゆっくりと呼吸しながら行うことで、リラックス効果も高まります。
記録をつけてモチベーションを高める
トレーニングのモチベーションは「成功体験の積み重ね」によって維持しやすくなります。小さな変化でも見逃さないように、以下の記録をつけることにも取り組みましょう。
- トレーニング日とトレーニングした部位
- こなした種目や回数、セット数、扱った重量
- 毎日の体重や体脂肪率
- 体調やトレーニング中の気づき
ある程度ジムに通ってから記録を見返すと「こなせる回数が増えた」「以前よりも重量を増やせた」などの変化に気づけます。達成感によってジム通いを続けやすくなるため、まずは難しく考えずに、簡単な記録から始めてみましょう。
全身を効率的に鍛えるには? 1週間の部位別メニュー例
ジムでの筋トレに興味があるものの「メニューの組み方が分からない」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。ここからは一例として、週3回、月水金のジム通いを想定した1週間のトレーニングメニューをまとめました。
全身をバランスよく鍛えるために、下記のポイントを押さえたメニューにしています。
【メニュー設定のポイント】
- 1.効果的に全身の筋肉を刺激するために、大きな筋肉(大筋群)から先に鍛える
- 2.複数の関節と筋肉を同時に使うために、コンパウンド種目(多関節種目)を活用する
- 3.負荷の集中と回復を意識して、スプリットルーティン(部位の分割)を取り入れる
各種目の回数やセット数は、あくまで目安です。自身の体力レベルに合わせた内容に調整し、セット間には60〜90秒程度の休憩を挟みましょう。
【月曜】下半身(脚・お尻)を中心に鍛える

月曜日のメニューは、体の中で最も大きな筋肉群が集まる「下半身」を中心に鍛えるものです。
脚とお尻の筋肉をしっかりと動かすことで、身体のエネルギー消費量を高めつつ、基礎代謝を向上させる効果が期待できます。
【月曜日のトレーニングメニュー】
①レッグプレス(10回×3セット)
太ももの前側(大腿四頭筋)、お尻(大臀筋)、太ももの裏側(ハムストリングス)を総合的に鍛えるマシントレーニングです。
②スミスマシン・スクワット(10回×3セット)
バーベルが固定されている、スミスマシンを使ったスクワットです。フォームが安定しやすいため、初心者でも安全にトレーニングを続けられます。
③ヒップアブダクション(12回×2セット)
専用のマシンを使って、お尻の横側(中殿筋)を鍛えるトレーニングです。ヒップアップや骨盤を安定させる効果も期待できます。
④トレッドミル(ランニングマシン)(10分)
ウォーキングやランニングを屋内でするためのマシンです。クールダウンも兼ねて、心拍数を少し上げる程度の有酸素運動を行いましょう。
【水曜】上半身(胸・肩・腕)を中心に鍛える

水曜日のメニューでは、上半身の押す動作に関わる胸や肩(前部・中部)、腕の裏側(上腕三頭筋)の筋肉群を中心に鍛えます。
下記のトレーニングは、厚い胸板や引き締まった二の腕、丸みのある肩を目指している方におすすめです。また、姿勢の改善や肩こりを予防する効果も期待できます。
【水曜日のトレーニングメニュー】
①チェストプレス(10回×3セット)
大胸筋を中心に、肩の前部や上腕三頭筋も鍛えられるマシントレーニングです。
②インクライン・チェストプレス(10回×3セット)
傾けたベンチで仰向けの状態になり、チェストプレスを行うトレーニングです。大胸筋の上部に強い刺激を与えられます。
③ショルダープレス(10回×2セット)
肩の三角筋全体を鍛えることで、たくましい肩幅を目指せるトレーニングです。なで肩を改善する効果も期待できます。
④ダンベルフレンチプレス(10回×2セット)
二の腕の裏側全体に伸びている筋肉を鍛えることで、たるみの予防にもなるトレーニングです。
【金曜】背中・体幹を中心に鍛える

水曜日には「押す動作」のトレーニングを行ったので、金曜日は「引く動作」に関わる筋肉群を鍛えます。
背中(広背筋、僧帽筋、脊柱起立筋など)と、体の中心を支える体幹(腹筋群など)を鍛えると、美しい姿勢の維持やバランスの向上、腰痛予防といった効果が期待できます。
【金曜日のトレーニングメニュー】
①ローイングマシン(10回×3セット)
背中の広背筋や、僧帽筋中部を中心に鍛えられるマシントレーニングです。
②バックエクステンション(12回×2セット)
背骨に沿って走る脊柱起立筋を鍛える種目で、正しい姿勢の維持に効果的です。
③クランチ(30秒×2セット)
腹直筋の上部を鍛える基本的な腹筋運動です。
④プランク(30秒×2セット)
腹横筋をはじめとする、体幹深層部を鍛える静的トレーニングです。
「プランク」については下記の記事で詳しく解説しています。
プランクの効果的なやり方とは。正しい姿勢で何秒耐えたらOK?個人のレベル別にトレーナーが解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
⑤ストレッチポールなどで背中ほぐし
トレーニング後に取り組むと、背中の緊張を和らげる効果が期待できます。
男性と女性・年齢・体力に応じた負荷の調整ポイント
筋トレの負荷を決める際には「10回をギリギリこなせる重さ=10RM(レペティション・マキシマム)」を目安にする方が多いかもしれません。ただし、この負荷設定はあくまで一つの指標です。
最初から大きな負荷をかけると、トレーニングの継続が難しくなったり、フォームが崩れてケガをしたりするリスクがあります。自身の体力レベルが不安な方は「少し余裕のある重さ」に設定しても構いません。
大切なポイントは、無理のない範囲で負荷を調整することです。ここからは、性別や年齢、体力に応じた負荷調整の考え方を紹介します。
性別による筋トレ負荷の調整
筋肉量やホルモンバランスには男女差があるため、性別によってトレーニングの効果が変わることもあります。一般的に女性は筋肉がつきにくいとされていますが、適切な方法でトレーニングをすれば、引き締まったボディラインを作ることは十分に可能です。
女性向けのメニューとしては、骨盤周辺や下半身のトレーニングが挙げられます。姿勢改善や産後の体型戻しにつながる筋トレ、またはヒップアップや美脚効果を目的としたトレーニングを選びましょう。
いきなり高重量を扱う必要はなく、最初は15〜20回程度をこなせるメニューで構いません。正しいフォームを身につけるために、自身の筋肉量や目標に合ったメニューを選んでください。
年齢別の負荷調整の考え方
実年齢が若くても、いきなり高負荷をかけるトレーニングは避けましょう。基本的には低負荷・高回数のトレーニングから始めて、ケガの防止にもつながる「正しいフォームの習得」を優先します。
また、年齢を重ねると筋力だけではなく、身体のバランス能力や柔軟性も変化してきます。特に高齢者(一般的に65歳以上)の方がトレーニングを行う場合は、安全面への配慮がより一層重要です。
厚生労働省の「標準的な運動プログラム」でも、高齢者を対象としたプログラムでは、筋トレ以外も含めた多要素な運動が推奨されています*2。有酸素運動や柔軟運動、バランス運動なども取り入れて、無理のない負荷で週3日以上のトレーニングを目指しましょう。
より安全性を高めるには、急な動きや反動を使った動きは避けて、筋肉を意識したコントロールを心がけます。基本的には、フリーウェイト(※)ではなく軌道が安定しているマシントレーニングがおすすめです。
※ フリーウェイト:ダンベルやバーベルなどの道具を使い、重量を自分でコントロールしながら全身を鍛えるトレーニングのこと。
体力レベルに応じた負荷調整の考え方
筋トレの効果を引き出すには、体力レベルに合わせて負荷調整を行うことも重要です。基本的には「少しきつい」と感じつつも、正しいフォームで目標回数をこなせる程度の負荷に調整しましょう。
以下では初心者・中級者・上級者に分けて、負荷調整の目安をまとめました。
【体力レベル別の負荷調整】
・初心者や体力に自信がない方
まずは「15〜20回程度」「楽に反復できる重さ」から始めて、正しいフォームを身につけましょう。道具やマシンを使ったトレーニングのほか、自身の体重を負荷にする自重トレーニング(膝をついた腕立て伏せなど)もおすすめです。慣れてきたら回数や負荷を増やして、段階的に強度を上げてみましょう。
・トレーニングに慣れた中級者
トレーニングに慣れてきたら「8〜12回程度で限界を感じる重さ」を目安にします。同じ重さで目標回数を楽にこなせるようになったら、少しずつ重量を上げてみてください。
・上級者
上級者になったら、より具体的な目的に合わせてメニューを考えます。筋肥大や筋力アップ、筋持久力アップなどの目的を踏まえて、専門的な負荷設定やトレーニングプログラムも視野に入れましょう。
トレーニングを続けると体力レベルは日々変化するため、柔軟に負荷調整をすることが大切です。
安全に配慮した負荷調整のポイント
安全面に配慮する意味でも、適切な負荷調整は欠かせません。まずは自身の健康状態を把握し、徐々に負荷を上げるようなメニューを考えましょう*3。
参考として、以下ではトレーニング全体のメニュー例を紹介します。
【安全面に配慮したトレーニングの例】
- ① 5〜10分程度の軽い有酸素運動や動的ストレッチで、しっかりと身体を温める
- ② 筋肉や関節を整えながら、自分の健康状態をチェックする
- ③ 健康状態を踏まえて、トレーニングの目標や目的を設定する
- ④ 軽い負荷をかけて、トレーニングの正しいフォームを確認する
- ⑤ こまめに身体の状態をチェックして、負荷を調整する
間違ったフォームはケガの原因になるため、正しい姿勢を保てない場合は負荷を下げるなどの対応が必要です。負荷を上げる際にも、こまめにフォームを確認しましょう。
久しぶりにマシンを使う場合も、軽めのウェイト(負荷)から始めることをおすすめします。「以前は〇〇キロの重量が扱えた」のように慢心せず、正しい動きができる負荷を常に確認してください。
筋トレジムメニューを3カ月続けるコツ

筋トレのジムメニューは「完璧にやる」よりも「トレーニング自体をやめないこと」を意識するのが大切です。当初はハードルが高いと感じても、続けるコツを押さえてさまざまな工夫をすれば、無理なくトレーニングを習慣化できます。
ここからは「3カ月の継続」を目安として、続けるコツやアレンジ例を紹介します。
目標と進捗状況を「見える化」する
目標と進捗状況を見える化すると、トレーニングの成果が分かりやすくなるため、モチベーションを維持しやすくなります。実際の目標設定と進捗管理では、以下のポイントを意識しましょう。
- 数値を使い、具体的かつ達成可能な目標を立てる
- 短期目標と長期目標を設定する
- 記録した進捗は定期的に見直す
いきなり大きな目標を設定するのではなく「週に3回ジムに行く」などの達成可能な目標を立てると、モチベーションにつながる成功体験を積み重ねられます。
ただし、短期目標だけでは方向性(本来の目的)を見失う可能性があるので「1年後にはフルマラソンに出る」といった長期目標も設定するといいでしょう。
計画通りにトレーニングが進むとは限らないので、記録した進捗は定期的に見直し、必要に応じて修正することも大切です。分かりやすい記録として、体組成測定のデータやトレーニング前後の写真を残す方法もおすすめします。
ライフスタイルに合わせた運動習慣を取り入れる
日頃から運動をする習慣が根付くと、筋トレのジムメニューも飽きずに継続できます*4。実際にどのような方法があるのか、以下では習慣化する工夫をまとめました。
- 生活リズムに組み込む
- 「ながら運動」や「スキマ時間運動」を取り入れる
- 日々のトレーニングメニューに変化をつける
- トレーニングの環境を変えてみる
具体例としては「毎週月・水・金の出勤前はジムに通う」「テレビを見ながらプランクをする」などの方法があります。トレーニングに飽きを感じたら、メニューの内容や回数を見直して変化をつけるとよいでしょう。
トレーニング環境を変えたい場合は、ジムのスタジオプログラムに参加するなどの方法がおすすめです。
モチベーション維持のためのコミュニティー活用
一人で筋トレを続けることが難しい方は、仲間と一緒にトレーニングできるコミュニティーを活用しましょう*5。
例えば、情報交換や励まし合いができる「ジム友」がいると、会話を楽しみながら筋トレに取り組めます。よく会う人に挨拶をしたり、ジムのイベントに参加したりすると、気の合う仲間が見つかるかもしれません。
SNSやアプリでトレーニングの成果を発信し、仲間を募るような方法もあります。同じような目標を持っている人から「いいね」やコメントがつけば、日々のモチベーションを高められるはずです。
また、パーソナルトレーナーのいるジムでは、伴走者としてのサポートも受けられます。費用はかかりますが、専門的なアドバイスや的確な声かけも受けられるので、モチベーションに悩んでいる方は検討してみてください。
週3筋トレで“疲れにくく動ける身体”へ
初心者の方でも、筋トレのジムメニューを週3回正しい方法で続けると、着実に身体の変化を感じられるはずです。見た目が引き締まるだけではなく「階段の上り下りが楽になった」「姿勢を褒められた」のように、生活面でのポジティブな変化を実感できることもあります。
筋トレは、健康的な生活を送るための基盤作りにつながります。将来への投資に近いもので、目先の体重や体型変化だけが目的ではありません。
最初から完璧を目指す必要はないので、まずは楽しみながら「3カ月の習慣化」を目指してみましょう。
編集:はてな編集部
編集協力:株式会社YOSCA
*1:参考:厚生労働省 e-ヘルスネット「ストレッチングの効果」
*2:参考:厚生労働省「標準的な運動プログラム(健康増進施設)」より「高齢者を対象にした運動プログラム」(PDF)
*3:参考:厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」より「身体活動・運動を安全に行うためのポイント」(PDF)
*5:参考:スポーツ庁「スポレクプログラム定着・継続のための実践ガイド」
