
腎臓病は、実は身近に起こり得る病気です。腎臓病の初期では自覚症状は感じづらく、予防を考える上では食事や生活習慣が重要なポイントになります。
この記事では、腎臓病の基礎知識や腎臓病対策の具体的な方法、腎臓の機能低下に気付くためのチェックポイントを紹介します。
こんな人におすすめ
- 腎臓病について聞いたことがあるが、詳しいことは知らない人
- 健康診断などで腎臓に気を付けた方がよいといわれている人
腎臓病とは

腎臓病は、腎臓にある糸球体(血液をろ過して尿をつくる、フィルターのような役割を果たす器官)や尿細管(糸球体でろ過された尿を再吸収する器官)が冒されることによって、腎機能が低下する病気です。腎臓病にはさまざまな種類があり、原因や治療法はそれぞれ異なります*1。
腎臓病対策の重要性
腎臓病には初期症状を自覚しづらいものもあります。医療技術の進歩に伴い、腎機能の低下を遅らせることは可能になったものの、悪くなると回復しにくいため、腎臓病への対策が重要です*2。腎臓病への対策

腎臓病は早期発見・早期治療が大切です。腎臓病の中には、進行するまで自覚症状が出ないものもありますが、もし病気が見つかっても症状を悪化させない習慣を身に付けておくことで、健康な人と同じような生活ができる場合もあります*3。
日常生活の中で、食生活や運動、禁煙を心がけながら生活してみましょう。
食生活を整える
腎臓の食事療法で最も大切なのは、塩分のコントロールです。塩分は尿として排出されるので、塩分が多いと腎臓に負担がかかります。他にも、タンパク質を摂り過ぎないことや、適度な水分を補給することがポイントです。
減塩を心がける
塩分は、1日6g以下を目指します。しかし「どう減塩してよいか分からない」という方もいるでしょう。以下のような工夫をすれば、無理なく塩分をコントロールできます。- 麺類の汁は残す
- 減塩タイプのしょうゆやみそを使用する
- 塩の代わりに、こしょうなどの香辛料を取り入れる
- 天然素材のだしを使う
- 調味料は「かける」ではなく「つける」を意識する
ちくわなどの練り製品や、インスタント食品、ハムなどの加工食品にも塩分は含まれているので、注意が必要です*4。
タンパク質を取り過ぎない
タンパク質の取り過ぎは、体内でタンパク質が分解された後にできる老廃物である尿素やクレアチニン(アミノ酸の一種であるクレアチンリン酸が代謝された後にできる老廃物)などの増加につながります。尿素やクレアチニンは、腎臓からしか排泄(はいせつ)できないため、腎臓への負担が増えます。とはいえ、タンパク質の適度な摂取は必要です。腎臓の状態に合ったタンパク質の量について医師と相談しましょう。
腎臓の健康を維持するために推奨される食事、避けるべき食事については、下記の記事で詳しく解説しています。
👉腎臓に良い食事・悪い食事とは? 食生活で気をつけるポイントを解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
適度に水分補給をする
適切な水分量は、腎臓の状態によって異なります。医師と相談し、自分に合った適切な水分摂取量を知ることが大切です*5。例えば、尿が濃縮された状態や排泄機能が低下した腎臓では、十分な水分が必要になります。水分が少ないと、老廃物を排出しづらくなり、腎臓に負担がかかるためです。
逆に、摂取した水分が適切に排泄されず、身体に蓄積されているケースでは、水分を制限しなくてはなりません。塩分の取り過ぎのほか、老廃物の増加、血糖値の上昇でも喉が渇くので、摂取に際しては注意が必要になります*6。
水分摂取については、下記の記事でも詳しく解説しています。
👉腎臓と水分の関係性とは? 健康への影響と1日の摂取量の目安を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
適度な運動をする
以前は運動が腎機能に悪影響を及ぼすといわれてきましたが、近年の研究結果では、腎臓病や腎機能低下の対策として効果的とされています。運動の中でも、有酸素運動(早足でのウォーキング、サイクリング、水泳など)とレジスタンス運動(腕立て伏せ、腹筋などの筋力トレーニング)がおすすめです*7。
腎臓病が進行している方は、日本腎臓学会の「腎疾患患者の生活指導・食事療法に関するガイドライン[PDF]」をもとに作成した以下の表を参考に、日常生活について医師と相談しましょう。

喫煙を控える
喫煙は、腎臓病の発症・進行に関わります。
タバコに含まれるニコチンは、血管を収縮させて腎臓の血流量を落とし、尿タンパクを増やします。また、血管そのものの障害も引き起こします。
タバコを1日20本以上吸う人は、末期腎不全になる確率が、吸わない人の2倍以上だといわれています。タバコの本数が多ければ多いほど、腎機能の悪化につながるので、注意が必要です*8。
アルコールは飲み過ぎに注意する
適度な飲酒は、尿タンパクを減らす可能性があると報告されています。アルコールを摂取する場合は、1日あたり20g未満を目安にしましょう。ただし、過剰なアルコール摂取は禁物です。尿タンパクを増加させるため、リスクとなります*9。
腎臓とアルコールの関係については、下記の記事でも詳しく解説しています。
👉アルコールは腎臓によくない? 腎機能への影響と種類ごとの適正量を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
腎臓の悪化に気付くためのチェックポイント

腎臓が悪化したときに出る症状は、以下のようなものがあります*10。あてはまる症状がないか、チェックしてみてください。
むくみ(浮腫)
むくみ(浮腫)とは、腎臓が水分を適切に排泄できず、体内に余分な水分がたまっている状態を指します。むくみが疑われる部分を指で5秒以上、少し強めに押さえてみて、指の跡がへこんだまま残ったら、むくんでいるサインです。
腎臓以外の原因(リンパの流れが悪い場合など)でも、むくみは起こります。むくみの原因を特定し、原因に応じた対処が必要です。
腎臓とむくみの関係については、下記の記事で詳しく解説しています。
👉むくみの原因は腎臓にある? その関係と今すぐできる対策法を解説 - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
尿量
腎臓は血液中の老廃物をろ過し、尿に変えて体外に排出しています。腎機能が低下すると、尿を濃縮する力が弱まり、多尿になります。さらに腎臓の状態が悪化し続けると、尿量が低下します。夜間尿
腎機能が低下し多尿になると、夜中に何度もトイレに行くようになります。日中に排泄しきれなかったナトリウムを、夜間に血圧を高くして排泄しようとします。頻尿
頻尿とは、尿の回数が増えることです。1日8〜10回以上、夜間2回以上トイレに行く状態を指します。頻尿は、尿量の増加(1日2L以上)によるものと、尿量はそのままで、回数だけが増えるケースがあります。どちらに該当するかは、1回の排尿の際の尿量で判断可能です。
体のだるさ
体のだるさは、末期腎不全の症状としてよく見られます。腎機能が著しく低下し、尿毒症物質が蓄積するとだるさが認められることがあり、その場合は透析などの腎代替療法を検討しなくてはなりません。貧血
腎臓は尿の排泄だけではなく、ホルモンの分泌も行っています。腎機能が低下すると、赤血球を作る働きを促進するホルモン「エリスロポエチン」が十分に分泌されなくなります。その結果、赤血球を作る働きが低下し、腎性貧血が起こります。かゆみ
皮膚疾患がないのに体がかゆい場合は、腎臓の病気である可能性が考えられます。腎臓が悪くなると老廃物が体内に蓄積され、それが脳に伝わってかゆみを感じます。また、腎機能の悪化により皮膚が乾燥することでかゆみの原因となることもあります。まめな入浴や保湿用の塗り薬が、かゆみ対策に有効です。腎臓病の初期症状について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
👉これって腎臓病? 腎臓病の初期症状チェックリスト - lala a live(ララアライブ)│フォーネスライフ
普段から腎臓病の対策を

腎臓病の対策を考える上では、減塩や禁煙といった食事や生活習慣の見直しが必要です。また、腎臓を悪くした際の体のサインも見逃さないようにしましょう。頻尿や夜間尿、体のだるさなどが出現した場合は、速やかに医療機関を受診し、医師に相談しましょう。
編集:はてな編集部
編集協力:株式会社イングクラウド
フォーネスライフが提供する疾病リスク予測サービス「フォーネスビジュアス」は、4年以内の慢性腎不全をはじめとした各種疾病の将来の発症リスクを予測することができます。
さらに、保健師の資格を持つコンシェルジュから予測の結果と体の状態を踏まえた生活習慣改善のアドバイスを受けることも可能です。
その提案を実践し生活習慣が改善されれば、腎臓病などの各種疾病リスクへの対策にもつながるでしょう。
※フォーネスビジュアス検査は、医療機関の医師を通じて提供します。
慢性腎不全のリスク、調べてみませんか?
*5:参考:一般社団法人 全国腎臓病協議会(全腎協)「水分・塩分の摂取について | 腎臓病について 」
*6:参考:東邦大学医療センター大森病院 腎センター「腎臓を保護しましょう~生活編 | 患者さんへ」
*7:参考:ほっとけないぞ!CKD慢性腎臓病「運動療法について | CKD(慢性腎臓病)とは」
*8:参考:SBS静岡健康管理センター「健康トーク 「教えて!健康」」
*10:参考:一般社団法人日本腎臓学会「3.腎臓がわるくなったときの症状-一般のみなさまへ」


 詳しく見る
詳しく見る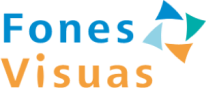
 「フォーネスビジュアス」のサイトを見る
「フォーネスビジュアス」のサイトを見る