
日々忙しく働く中では、つい食生活が乱れてしまいがち。偏った食生活により、じわじわと増えていく体重が気になっている……という人は少なくないでしょう。
編集者でブロガーの近藤佑子さんも、そんな悩みを抱えてきた一人。健康な食生活に興味はありつつも「ストレスがかかるとついお菓子を食べ過ぎてしまう」癖があり、一度ダイエットに成功してもまたリバウンドしてしまう、という生活を繰り返していたといいます。
試行錯誤する中で見えてきたという「自分に合った食生活」と、それを継続していくための工夫についてつづっていただきました。
幼少期から平均的な身長に平均的な体重だった私は、思春期の頃から人並みに「もっと痩せたい」という気持ちを持つようになった。
学生時代には、課題や研究、論文のストレスで、標準体重から15kgほど上回ってしまった。追い詰められて深夜まで作業しては、気絶するように寝る日々。口にするのはコンビニ弁当、お菓子、カフェイン……何かを頑張りたい気持ちと健康的な食生活は、トレードオフだと思っていた。
そんな私が健康に強い関心を持つようになったきっかけは、10年前に会社員になり、健康診断を受けるようになったこと。大学で受けていたものとは違って「こんなに手厚く見てもらえるのか」と感激し、以降、健康診断を受けて結果を見ることが毎年の楽しみになった。
自分の体の状態が数字で見える化され、年々記録が積み重なっていくのが単純に面白かった。特に悪い数値がなかったのもあるかもしれない。もっとハイパフォーマンスな自分になりたい、理想的な自分になりたいと健康に関する書籍やインターネットの記事を読み漁った。
そうして、一時はダイエットに成功したこともあった。しかし忙しくストレスの多い社会人生活の中では、油断するとすぐに食生活が乱れて体重が増えてしまうのが悩みだった。こういう食生活が、「何となく調子が悪い」と感じる体調に影響するはずだし、できるだけ長く健康な状態はキープしたい。
それに、最近、趣味が高じてダンスパフォーマンスで舞台に立つようになり、動くにしても魅せるにしても、満足のいく体を作りたいという思いもあった。
今回は、私がどのように自分に合った食生活を見つけて、それを続けるために試行錯誤してきたのかを紹介したい。
自分に合った食生活を見つけるまで、トライアンドエラーの日々
10年前、会社員になって健康に興味を持つようになった私は、まずスポーツジムでのトレーニングを始めた。しかし、ジムのトレーニングだけでは2~3kgの減量が限界だった。その後、ちまたではやっていた糖質制限ダイエットに取り組んでみることにした。
当時は今ほど知識もなかったので、普段は主食を控えたり、おやつは糖質制限スイーツを選んで食べたりしながら、一方で友人からのお誘いの際にはあまり気にせず何でも食べたりしていた。そんな感じでざっくり運用していたが、4カ月で12kgもの減量に成功した。

しかし仕事がちょっと忙しくなると、食べ過ぎや飲酒が積み重なり、すっかり元の体重に戻ってしまった。このやり方では、自分は続かない。自分に合っていて、継続できる方法で食生活を改善する必要を感じた。
リバウンドしてしまったけど、糖質制限を経験したことで、糖質の摂取による血糖値の急上昇が体脂肪の増加につながるということを知ることができた。*1
以降も食生活に関する情報収集を続けながら、血糖値を急激に上げないための低GI値食品、腸内環境を整えるための方法、カフェインやお酒を控えるなど、さまざまな方法を試し、自分に合う食生活について試行錯誤を続けた。
「自炊=健康的な食生活」だと思っていたけれど
こういった食生活を整える取り組みは、コロナ禍で家にいる時間が長くなったからこそ捗った。その中で、ある気付きがあった。
コロナ禍に自炊がしやすい家に引っ越したので「最強の食生活をしてやろう」と意気込んだ。
調理家電に大量の野菜と、肉やサバ缶を突っ込み、日替わりで味をつけて、豚汁、豆乳鍋、カレーなどにして、ひたすら食べた。十分な量の野菜に、適量のタンパク質と炭水化物に塩分。摂取カロリーも基準値以内に収まっていて、栄養バランスは申し分ないと思っていた。
煮物だけでは飽きてきたので、気合いを入れてもう少し本格的な料理も作るようになった。

ただ、体重はびくともしないどころか、逆に増えてしまい、2022年の年始には、ここ数年で最大値の体重に達した。振り返ってみると、私が自炊で作っていたメニューは、「脂質」が多かったのだ。実際、アプリでつけていた当時の食事記録を見ると、カロリーや糖質は控えめでも脂質が多い日が続いた。
そこで、タンパク質、脂質、炭水化物のバランスを見るという「PFCバランス*2」を意識することに。今まで私の食生活といえば、糖質量やタンパク質量は気にしていたけれど、脂質には注目していなかったのだ。何も気にせずに自分がおいしいと思えるものを作って食べると、脂質が多くなりがちということに気付いた。
自炊をしても脂質を摂り過ぎていたことにショックを受けた私は、自炊を諦めて宅配冷凍弁当に頼ることにした。私が選んだサービスでは、弁当を選ぶページで脂質の少ない順に並べることができたので、低脂質でおいしそうなメニューを選んで注文できた。
PFCバランスを気にする食生活は、地味でストイックではあるものの、一定の成果が出て、コロナ禍の間に増えた体重を元に戻すことができた。
理想的な食生活を「継続」するための工夫
自分がどんな食生活をすればいいのかは分かってきたものの、問題は、その食生活をいかにして続けるか。これまで、ちょっと仕事やプライベートが忙しくなっただけで、良い食生活がいとも簡単に崩れてしまうのを何度も経験した。
それでもなんとか続けていくために、私が実践したことについて紹介したい。
本でモチベーションを高める
健康に関する情報は、インターネットでも参照したが、本で得ることが多かった。糖質制限に関する本だけでも10冊近く読んだ。本で紹介されている実体験を読むことで、モチベーションを高めるという効果もあった。一度挫折してしまったとしても、本で得た知識が後になって役立つこともある。本を読む気分じゃないときは、YouTubeもおすすめだ。私自身、何気なく見ていたYouTube動画で「PFCバランス」について紹介されていたのをきっかけに、新しい行動に向かうことができた。
計測して成果を可視化する
何かを改善したいなら、計測は基本中の基本だと感じた。もともとライフログが好きなのもあって、体重や体脂肪率は体組成計で毎日測っているし、スマートウォッチで歩数、睡眠、心拍数なども測っている。そして食事記録アプリを入れて、日々の食事を記録している。
体重の記録や食事記録は面倒だが、サボっているときは明らかに体重が右肩上がりになってしまうから、まずは記録だけでも続けなければならないと、自分に言い聞かせている。
私の場合は、SNSで友人が使っていて気になった「習慣化を助けるアプリ」を入れた。そこでは「マイナス5kg」「食事記録」といった、同じ目標に向けた習慣化を目指す人たちで構成されたチームが並んでおり、実際に行動を起こしたかどうかを、スクショや写真を添えてチームメンバーに報告する。
体重測定なら、体重計の写真や体重記録アプリのスクショ、食事記録なら入力完了後にアプリのスクショを載せるという感じ。他のメンバーが見ているので、サボりにくいというわけだ。
習慣化に興味を持った私は、『小さな習慣』(スティーヴン・ガイズ著、ダイヤモンド社)という本も読んでモチベーションを上げた。「小さ過ぎて失敗しようがない」ほどのちょっとした行動でも、必ずやると決めて実行することで、習慣が続くだけでなく、成功体験を重ねて自信が得られるのだという。
食事のバランスに気を付けられれば、必ずしも自炊しなくてもいい
このようにアプリや習慣化の力を借りていても、面倒なのが食事記録だ。
自炊をしていた時は、自分で作った献立に含まれる食材などを毎回記録するのが億劫(おっくう)だった。
しかし自炊をやめて宅配冷凍弁当を取り入れたところ、私が利用していたサービスが食事記録アプリと連携していたので、簡単に栄養情報を記録することができた。これは主要なコンビニの食品や、市販の食品も同じで、かなり食事記録が捗った。
このおかげで、PFCバランスを許容値に押さえるのが、そこまで難しくなくなった。例えばお菓子を食べたいとコンビニに買いに行ったとしても、現在のPFCバランスを見て「この商品を食べるとどの数値がいくら上がるのか」をあらかじめチェックしてから買うことができたし、チェーン店の居酒屋に飲みに行ったとしても、PFCバランスが基準内に収まるメニューを確認してからオーダーすることができた。
今は食事について、宅配冷凍弁当やコンビニ・スーパーの商品など市販のものに頼っている私だが、自炊はいい経験になっている。自炊のおかげで食材の重さをよく測るようになったので、例えばご飯150グラムこのくらいの量だ、といったことがなんとなく分かるようになった。これは、食事記録アプリに手動で入力する際にも役に立っている。
自炊についてはいつかまた挑戦して、今度こそ最強の食生活を実現したい。
専門家に伴走してもらう
自分一人で取り組むのではなく「人にサポートしてもらう」のも有効だった。食生活の改善とあわせて運動の必要性を感じ、パーソナルトレーニングジムに入会したのだが、そのプログラム内に簡易的な食事指導がついていた。トレーニング期間中は毎日、体重・体脂肪率・食事の内容を送るというものだ。毎日の報告に対するリアクションは、スタンプでの返信という簡易的なものだが、人に見てもらっているだけで「ちゃんとしなきゃ」という意識が働いた。
たまに「ちょっとカロリーがオーバーしていますね」と返信があると、ドキッとした。同時に、エキスパートが私のために伴走してくれていることのありがたさを感じた。
お菓子はまず3日我慢する
食生活改善の最後の砦、お菓子について。私はかつて「1日1アイス(までにしよう)」という目標を立てるほど、甘いものが大好きだった。糖質制限の経験を経て、よい食生活をキープできているときは食べないですむ時期もあるが、忙しくなると、とたんにコンビニにお菓子を買いに駆け込むことがあった。それは決してお腹が空いているとか、体が求めているからではない。ストレスからくる「食べずにはいられない」という衝動的な欲求によるものだった。
お菓子をやめるにはどうしたらいいか。私は、なんとかして「お菓子を食べない日」をしばらく作ってみることにした。
1日目、2日目と、お菓子が食べたい欲求が頭にチラついたが、気合いで乗り切った。「食べたい」という気持ちが起こったら、「もしかしたら喉が乾いているだけかもしれない」と水を飲んだり、これは脳が欲している衝動的な食欲であると自分に言い聞かせた。すると、3日間を過ぎた頃には、「お菓子を食べたい」という気持ちが少なくなっていたのである。
お菓子をやめるといっても、完全にやめるわけではない。PFCバランスをふまえて摂取炭水化物量に余裕があるときや、特別な日には、丁寧に作られたとっておきのお菓子をいただくのはよいとしている。お菓子を食べたい衝動に駆られたとき、1つのケーキをゆっくり味わって食べたときには、不思議と「たくさん食べたい」という欲求が収まった。
食生活の改善は、自分をもっと自由にしてくれる
PFCバランスを基準値内に収め、お菓子は基本食べないようにし、飲み物は基本的に水かお茶、カフェインやお酒は控えめにする。現状の私がたどり着いた理想的な食生活は、一見するとかなり自由度が低いように思えるかもしれない。
しかし、ストレスの影響で「(お腹が空いていないのに)お菓子がやめられない」といった衝動的な欲求に振り回されていた頃に比べて、自分で試して、納得して、よいと思える食生活を取り入れるのは、自分の意志で行動できている証拠であり、実は自分にとっては、最も自由なんじゃないかと思っている。
実際、心が穏やかでいられるし、「食べる」というせっかくの楽しい行為で、罪悪感を覚えることもだいぶ少なくなってきた。その分、仕事やプライベートの活動にも集中できるようになったと思う。
とはいえ、ここまでやっていてもまだ、仕事やプライベートで忙しくなると、理想的な習慣が崩れてしまうことがある。でも、これまで積み重ねてきた経験や成功体験は、自分にとって大きな自信になった。今後またつまずくことがあっても、「またやってみよう」と再び行動を起こすきっかけにつながっていくだろう。
今回は近藤佑子さんに、自分に合った健康的な食生活を継続するためのヒントを語っていただきました。
記事内でも「専門家に伴走してもらうこと」の有用性についてつづられていますが、食生活を含めた生活習慣の改善について「専門家に相談しながら取り組みたい」と思われた方に、フォーネスライフが提供する疾病リスク予測サービス「フォーネスビジュアス」をご紹介します。
これは“今”と“将来”の健康状態と疾病リスクを分かりやすく可視化し、コンシェルジュ(保健師)から生活習慣改善のアドバイスを受けることができるサービスです。
下記の記事では、フォーネスライフの社長である江川尚人さん自らが生活習慣を改善した体験を語っています。サービスに関心を持っていただけたら、ぜひこちらもあわせてお読みください。
あなたの食生活改善を、専門家がサポートします
編集:はてな編集部

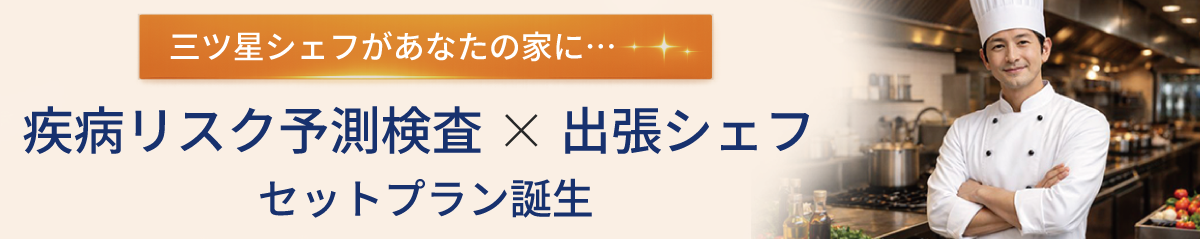

 詳しく見る
詳しく見る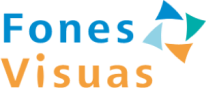
 「フォーネスビジュアス」のサイトを見る
「フォーネスビジュアス」のサイトを見る
