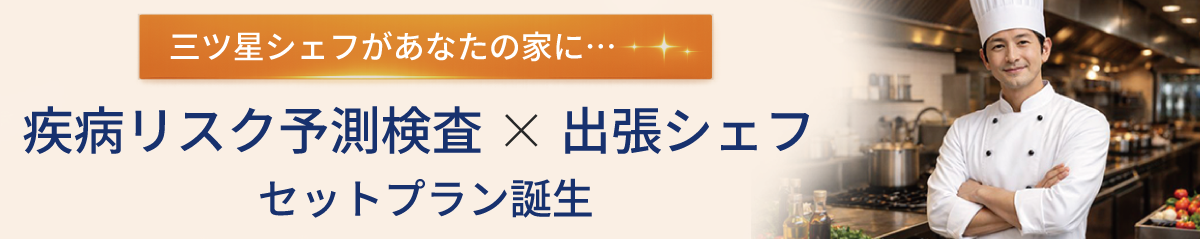疲労回復には、食べ物と飲み物の選び方がカギになります。
「最近、なかなか疲れが取れない……」と感じるような慢性的な疲れがある場合、もしかしたら栄養の偏りが原因かもしれません。
本記事では、疲れのタイプに応じた食べ物・飲み物のおすすめメニューやモデル献立を、すぐに試せる実践例を交えて分かりやすく解説します。コンビニ・外食の選び方も紹介しますので、早速今日の食事や飲み物選びの参考にしてください。
目次
なぜ「食事と飲み物」で疲れが取れるのか

疲労は、体の中で起きている不調のサインです。その回復には、体の修復材料となる栄養素と、栄養を巡らせる水分が欠かせません。
まずは疲れのメカニズムと、食事・飲み物が疲労回復に果たす役割を見ていきましょう。
疲労のメカニズム
「疲れ」は単なるだるさや眠気ではなく、休息の必要性を知らせる重要なサインです。活動によるエネルギー不足や筋肉・神経の損傷、自律神経の乱れを防ぐための、体が発する自然なアラート機能といえます*1。
疲労は「肉体的疲労」と「精神的疲労」の2つに大別できます。肉体的疲労は筋肉の酷使や内臓の負担、精神的疲労はストレスや脳の使い過ぎが引き金になります。
現代人の多くは、この両方が複雑に絡み合った状態にあるとされています。放置するとパフォーマンスの低下だけでなく、免疫力の低下や慢性疾患にもつながる可能性があるため、早めのケアが大切です。
食事と飲み物は、肉体的・精神的いずれの疲労回復にも重要
食べ物や飲み物は、肉体的・精神的どちらの疲労回復にも欠かせません。食べ物や飲み物に含まれる栄養素は、その種類によって、体のエネルギー補給や筋肉の修復だけでなく脳や神経を整えて気分を安定させる働きもあります。
以下は、疲労回復に関わる代表的な栄養素とその働きです。
- 糖質:疲労回復に必要なエネルギー源として重要
- ビタミンB群*2:糖質をエネルギーに変換。代謝全般に不可欠
- 鉄分*3:酸素の運搬に関与。不足すると貧血や倦怠感の原因に
- マグネシウム*4・亜鉛*5:神経伝達や代謝酵素の働きをサポート
- タンパク質*6:筋肉・ホルモン・酵素など体の構成材料
- クエン酸*7:疲労感の軽減をサポートする
- ポリフェノール:活性酸素の除去による抗酸化作用
- オメガ3脂肪酸(EPA・DHA):炎症抑制、集中力の維持*8
- カリウム:筋肉収縮や神経伝達を整え、疲労感を軽減
これらを毎日の食事から無理なく摂取することで、体は自然と回復モードに入っていきます。
また、水分補給も、疲労回復において重要な要素です。体内の水分が不足すると血液の濃度が高くいわゆるドロドロの状態になり、酸素や栄養素の運搬力が低下します*9。結果として、全身の細胞に十分な栄養が届かず、修復や再生の効率が低下してしまうのです。
さらに、老廃物や疲労物質の排出も滞るため、疲れが蓄積しやすくなります。
こまめな水分補給を意識することが、疲労を溜めこまない体を作る基本です。
タイプ別・疲労回復を助ける食べ物&飲み物
疲労タイプに応じて、摂るべき食材・栄養素は異なります。あなたの疲れに今必要な食べ物や飲み物は何か、見直してみましょう。
肉体的疲労におすすめの食べ物&飲み物
エネルギー代謝を支える栄養素を補うことで、回復力が高まり、翌日に疲れが残りにくくなります。
体をよく動かした日ほど、意識的に「栄養+水分」の補給を行いましょう。
<肉体的疲労におすすめできる食べ物>
- 豚肉(ビタミンB1)
- 梅干し・レモン(クエン酸)
- レバー(鉄分)
<肉体的疲労におすすめできる飲み物>
- 黒酢ドリンク(クエン酸・アミノ酸)
- スポーツドリンク(電解質・ブドウ糖)※適量を意識
- トマトジュース(リコピン・カリウム)
- 甘酒(ビタミンB群・ブドウ糖)
精神的疲労におすすめの食べ物&飲み物
ストレスや気分の落ち込みを感じたときは、脳と神経をいたわる栄養素を意識して補給しましょう。栄養が、心の疲れにじんわり効いてくるはずです。
<精神的疲労におすすめできる食べ物>
- バナナ(トリプトファン*10・ビタミンB6):セロトニン生成を助け、心を安定させる
- アーモンド(マグネシウム・ビタミンE):神経の興奮を抑え、ストレス軽減に役立つ
- ヨーグルト(乳酸菌*11・カルシウム):腸内環境を整え、自律神経をサポート
<精神的疲労におすすめできる飲み物>

1日で整える! 疲労回復のモデル献立(朝・昼・夜・間食・飲み物)
毎日の献立で少し栄養バランスを意識するだけでも、疲労回復に役立ちます。ここでは、忙しい方でも取り組みやすい1日の疲労回復献立例と、間食や飲み物のポイントをご紹介します。
朝食:代謝スイッチ+脳活性化
朝は代謝をスタートさせるゴールデンタイムです。エネルギー源+神経の安定に役立つ栄養素をしっかり補給しましょう。
ビタミンB群+良質なタンパク質+鉄分をバランス良く摂るのがポイントです。また、カリウム豊富なバナナやトマトを献立に取り入れることで、朝のむくみもケアできます。
<朝食のおすすめ献立例>
- 納豆ごはん(ビタミンB群・タンパク質)
- 小松菜と油揚げの味噌汁(鉄分・ミネラル)
- ゆで卵(タンパク質)
- ミニトマト(リコピン・カリウム)
- 豆乳バナナスムージー(イソフラボン・トリプトファン) or 甘酒(ビタミンB群・ブドウ糖)
昼食:集中力・持久力キープ
昼食は、午後に向けてのエネルギー持続と集中力の維持がカギになります。糖質+ビタミン+ミネラルの組み合わせが理想です。
<昼食のおすすめ献立例>
- 豚しゃぶと豆苗の冷やしうどん(ビタミンB1・ミネラル・タンパク質)
- ひじきと大豆の煮物(鉄・マグネシウム)
- キウイ or グレープフルーツ(ビタミンC・クエン酸)
- 緑茶(テアニン・カテキン) or レモン水(ビタミンC・クエン酸)
間食:賢く栄養チャージ
間食は食べ方と選び方次第で、疲労回復を後押しする栄養チャージのチャンスになります。特に昼と夜の間などに軽くエネルギー補給をすると、集中力や気力のキープに役立ちます。
ただし、食べ過ぎや糖質の摂り過ぎは、血糖値の乱高下を招いて逆に疲れやすくなるため、注意が必要です。カロリーは100〜150kcal程度を目安にしましょう。
<おすすめの間食例>
- ゆで卵(タンパク質・ビタミンB群)
- バナナ+ナッツ(トリプトファン・マグネシウム)
- 干し芋や焼き芋(食物繊維)
- 小さめのおにぎり(梅・鮭など具材を工夫するとクエン酸や鉄分も補える)
- カカオ70%以上のチョコレート(ポリフェノール)
夕食:回復+深い睡眠へ
夜は体の修復タイムです。夕食は消化にやさしく、睡眠ホルモンの材料になる栄養を意識することがポイントです。
<夕食のおすすめ献立例>
- 鮭ときのこのホイル焼き(タンパク質・ビタミンD・オメガ3)
- 雑穀玄米(鉄分・食物繊維)
- わかめと豆腐の味噌汁(マグネシウム・イソフラボン)
- カモミールティー(リラックス効果) or ホットミルク(トリプトファン)
3食以外のタイミングでおすすめの飲み物
3食以外でも、意識して水分を摂るようにしましょう。こまめな水分補給は体内の血流や代謝をスムーズに保ち、老廃物や疲労物質の排出を助けます。水分をしっかり補うことで心身のパフォーマンスが維持され、疲れを溜めにくい体作りにつながります。以下は、いずれもカフェインレスで体に優しく、水分補給に最適です。
<おすすめ飲み物例>
- 白湯
- 麦茶
- ルイボスティー
- レモン水
- シークヮーサー水
コンビニ・外食・冷凍食品でもOK! 忙しい人のための疲労回復メニュー
忙しいときには無理に自炊にこだわらず、コンビニ食品や冷凍食品を活用したり、外食を楽しんだりして、上手に乗り切りましょう。ここではコンビニ・外食・冷凍食品のおすすめ疲労回復メニューと選び方のポイントを紹介します。
コンビニ編
買ってすぐ食べられることと、複数のメニューを組み合わせやすいことがコンビニ食品の魅力です。高タンパク質なメニューに、温かい汁物や、ビタミン豊富なメニューを組み合わせましょう。
<コンビニのおすすめメニュー>
- サラダチキン・ゆで卵:高タンパク質&低糖質
- 梅干し入りや雑穀米おにぎり:ビタミン・ミネラル・クエン酸補給に◎
- 野菜スープ・レトルト味噌汁:体を温めて代謝をサポート
- 無糖の豆乳・食塩不使用の野菜ジュース:ビタミン・食物繊維を手軽にチャージ
外食編
外食の際も、栄養バランスと彩りを意識してメニューを選びましょう。特にメインに小鉢がつくランチセットは、野菜がしっかり摂れるのでおすすめです。
<外食のおすすめメニュー>
- 焼き魚・蒸し鶏などの定食:高タンパク質&低脂質
- そば+温泉卵・野菜天:消化に優しく、ビタミンも摂れる
- 和定食系メニュー:主食+汁物+小鉢でバランス抜群
冷凍食品も活用
冷凍野菜は、下ごしらえ要らずでさまざまな料理に使えるので、時短で自炊したいときの心強い味方です。味付けに酢・レモンなどを加えると、より疲労回復効果がアップします。
温めるだけで食べられるメニューは、お弁当作りにも役立ちます。
<冷凍食品のおすすめアイテム>
- 冷凍野菜(ブロッコリー・かぼちゃ・枝豆):時短でビタミン・食物繊維をプラス
- 鶏団子スープ・魚介入りの野菜炒め:温めるだけでしっかりタンパク質を確保
- 酢豚・レモンソース系のおかず:酸味の力で疲労物質の分解をサポート
栄養を最大限に生かす「組み合わせ食」と飲み方のコツ

食材を組み合わせることで、吸収率や効果がぐんと上がります。さらに飲み物との組み合わせにも注目して、効率的に栄養を摂取しましょう。
栄養素を活かすペア例
相性の良い組み合わせを意識して、メニューを考えてみましょう。例えば「豚肉+にんにく」なら、「豚にんにく炒め」や「豚キムチ」がおすすめです。
<おすすめの組み合わせ例>
- 豚肉+にんにく*14(ビタミンB1+アリシン):糖代謝を促進しエネルギー効率アップ
- レバー+レモン(鉄+ビタミンC*15):吸収率を高めて貧血予防に◎
- 鮭+きのこ(ビタミンD+B群):エネルギー代謝サポート
- 納豆+キムチ(発酵食品+食物繊維+乳酸菌):腸内環境を整えて自律神経をサポート
飲み物との組み合わせ
飲み物との組み合わせを意識すると、より効率的に栄養を吸収できます。特に朝食や間食のときには、おすすめの組み合わせを取り入れてみてください。
<おすすめの取り入れ方>
- 食後に柑橘系ジュース(ビタミンC):鉄分を効率良く吸収
- トマトジュース×チーズ(リコピンやβカロテン×乳製品*16):脂溶性プロビタミン×乳製品で吸収力アップ
- 味噌汁×玄米(アミノ酸バランスが向上):主食との組み合わせで満足感も得られる
逆に疲れるNG習慣とその改善ポイント
疲労回復を意識しているつもりでも、実は逆効果になっている習慣があります。例えば、エナジードリンクを頻繁に摂取すると、カフェイン*17や糖質の過剰摂取につながり、血糖値の急激な変動や睡眠の質の低下、疲労感の慢性化を招く可能性があります*18。
また、忙しさから朝食を抜いたり、その反動でドカ食いをしたりすると、血糖値の乱高下や胃腸への負担から、回復力が落ちてしまいます。栄養バランスを欠いた極端なダイエットや、夜遅くの食事も自律神経の乱れを招く要因です。
疲労を溜め込まないためには、規則正しい食事リズムと栄養を意識した選び方がポイントです。毎日の食べ物と飲み物の栄養バランスを整えて、無理せず継続できる習慣作りをすることが、結果的に最も効率的な疲労対策につながります。
食材やメニュー選びの工夫がカギに
疲労回復のために、特別な食事を用意する必要はありません。大切なのは、日々の食材や飲み物の「選び方」と「組み合わせ方」を少し工夫することです。自炊する時間がないときには、外食やコンビニでも、選び方次第で疲労回復に役立つ食事が取れます。
無理のない習慣として取り入れることが、疲れを溜めにくい体作りへの第一歩です。まずは今日の一食から意識してみましょう。
編集:はてな編集部
編集協力:株式会社イングクラウド
日々の食事や水分補給に少し意識を向けるだけで、疲労感は驚くほど軽減されます。とはいえ、「ちゃんと栄養を摂っているはずなのに、なかなか疲れが取れない」と感じる方も少なくないはずです。
そんなときは、自分の体の状態を客観的に見直してみるのも一つの手です。近年は、健康状態を可視化し、生活習慣の改善に役立てられるサービスが登場しています。
👉フォーネスビジュアス|病気になる前にわかる(NECグループ発)
フォーネスライフが提供する疾病リスク予測サービス「フォーネスビジュアス」は、体力を可視化する「心肺持久力」や食事量と運動量の手がかりになる「安静時代謝量」など、従来とは異なる形で体の状態を把握することができるサービスです。さらには将来の疾病リスクを可視化し、専門資格を持つコンシェルジュから生活習慣に関するアドバイスが受けられます。食事をはじめ、自分に合った運動や睡眠習慣などについても、専門的な視点から知ることができます。
※フォーネスビジュアス検査は、医療機関の医師を通じて提供します。
*1:参考:大阪公立大学 健康科学イノベーションセンター「疲労のメカニズム」
*2:参考:全国健康保険協会「漫画でわかる!お役立ち健康情報」令和5年度「忙しくてもすぐ読める!漫画栄養学」7月号「なんとなくだる~い」・・・に喝!「ビタミンB群」[PDF]
*3:参考:厚生労働省「健康づくりサポートネット」健康用語辞典「鉄(てつ)」
*4:参考:厚生労働省「健康づくりサポートネット」健康用語辞典「マグネシウム(まぐねしうむ)」
*5:参考:医療法人輝栄会 福岡輝栄会病院「検査科だより5:亜鉛の欠乏について」
*6:参考:厚生労働省「健康づくりサポートネット」健康用語辞典「たんぱく質(たんぱくしつ)」
*7:参考:大阪公立大学 健康科学イノベーションセンター「食事で疲れをとる」
*9:参考:一般財団法人 京浜保健衛生協会「京浜保健便り」2023年12月(65号)「冬も水分摂取を[PDF]」
*10:参考:豊能町「広報とよの 2022年3月号(No. 562)」より「健康福祉 保健福祉センターからのお知らせ[PDF]」
*11:参考:厚生労働省「健康づくりサポートネット」健康用語辞典「乳酸菌(にゅうさんきん)」
*12:参考:地方独立行政法人 筑後市立病院 広報誌いずみ「Vol. 40 カカオポリフェノールのちから」
*13:参考:日本農芸化学会「緑茶のストレス軽減および抗うつ作用[PDF]」(「化学と生物 Vol. 59 No. 1」セミナー室「お茶成分の脳における作用 3」)
*15:参考:埼玉医科大学病院予防医学センター「予防医学センターだより」 No. 24「鉄分補給で貧血予防[PDF]」
*16:参考:一般社団法人日本乳業協会「やっぱりミルク 牛乳編[PDF]」(パンフレットより)
*17:参考:厚生労働省 食品に含まれるカフェインの過剰摂取についてQ&A「Q.1 清涼飲料水など食品に含まれるカフェインを過剰に摂取することは健康に問題があるのでしょうか。」
*18:参考:一般財団法人 京浜保健衛生協会「京浜保健便り」2023年3月(56号)「砂糖の日にお砂糖の話を[PDF]」